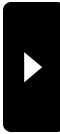2021年04月28日
思い出のゴッツンコ
「キャサリンさん。ゴッツンコの妖精って、何のこと?」と、「空飛ぶコーギー」のマロンが聞きました。パジャマを着た魔女のキャサリンは、やっとのことで朝寝坊のベッドから起き出しました。「あら、マロンはママから聞いていなかったの?あなたとママが出会ったのだって、ゴッツンコの妖精のおかげなのにね」と、キャサリンは言いました。「何でも妖精なの?」と、マロンは聞きました。「当り前じゃない。世の中のことは、何だって妖精の仕業よ。そんなこと決まっているじゃない。知らなかったのはマロンだけでしょう?」と、キャサリンは腕を組んで首をひねりました。
「あなたが、ママと出会ったときのことを思い出してみて」と、キャサリンが言いました。「ちょうどいい出会いがちょうどいいタイミングであるなんて、不思議だと思わなかった?ちょっとずれただけでも、マロンはママに会えなかったんだし、私とだって出会えなかったのよ」。「マロン。今日、あなたがここにいるのも、ゴッツンコの妖精のおかげなのよ。気づかなかった?」と、キャサリンがあくびをしながら言いました。
「それで、ゴッツンコの妖精って、どこにいるの?」と、マロンは聞きました。「どこにでもいるし、どこにもいないのよ」と、キャサリンは言いました。「ゴッツンコはね。気難し屋さんで、みんなの目にはなかなか見えないけど、ホラ、今、そこにもいたわよ」と、キャサリンがカーテンの陰を指差しました。カーテンは風をはらんで、大きく膨らんで、いかにもゴッツンコの妖精が隠れていそうでした。「ゴッツンコはね、恥ずかしがり屋さんで、みんなのすぐそばにいるけど、決して自分からはいることを知らせないの。だから、ゴッツンコしてみて、初めていたことに気づくのよね」と、キャサリンがベッドの下を指差しました。ベッドの下に何かがもぐりこんで隠れているような気がしました。「このゴッツンコは、僕とキャサリンさんの出会いのゴッツンコなの?」と、マロンは聞きました。「さあ、どうかしら?出会いの前には、私にも分からないわ」と、キャサリンが答えました。
その時、マロンの背後で、入口の扉が音も立てずに開きました。マロンは何かを感じて振り返ろうとしました。でも、マロンの顔は、キャサリンを見つめたまま。しばらくの間は、後を振り返ることができませんでした。マロンは後が気になり、何度も振り返ろうとしましたが、体が言うことを聞いてくれませんでした。「ねえ。キャサリンさん。僕の後ろにいるのは何?ゴッツンコが会わせようとしているのは何なの?」と、マロンが聞きました。「あなたの後にいるのは、誰もが振り返りたくなり、誰もが決して見ることはできないものよ」と、キャサリンが言いました。「えっ?何?」と、マロンは振り返ろうとしました。「それは、あなたの思い出」「僕の思い出?見てみたい」「無理。思い出は振り返って見るものじゃなくて、前を向いているときに背中で感じるものなの。いくら魔女でも、それだけはできないわ。今日のゴッツンコの妖精は、マロンの思い出を連れてきたのね」と、キャサリンが言いました。「見たい。見てみたい」と、マロンはもがきました。でも、マロンの体はますます硬くなり、顔を横に向けることさえできませんでした。
「マロン。静かに目を閉じて感じるのよ。思い出は振り返っても見られないんだから…」と、キャサリンが言いました。マロンは目をつぶりました。マロンの頭の中に、今までに出会った友だちの姿が浮かんできました。ポテトもキャンディーもケロちゃんも、みんなニコニコと笑顔を見せて、マロンの名前を呼んでくれました。「僕のすべての出会いは、ゴッツンコの妖精のしてくれたことなの?」と、マロンは目をつぶったままで聞きました。「そうよ。誰のおかげでもない、妖精たちのおかげよ」と、キャサリンが答えました。マロンの頭の中に、優しいママ犬の笑顔が浮かびました。「ママだ!」と、マロンは叫びました。マロンのママは、ただ黙って笑ってうなずくばかりでした。「ママ!」。マロンは振り返りたい気持ちをぐっと抑えました。「ゴッツンコ。ありがとうね。僕とママを出会わせてくれて」と、マロンがつぶやきました。
「マロン。あなたは本当に幸せよ。だって、思い出のゴッツンコとは、滅多に出会えないもの」と、キャサリンが言いました。「そうなの?」と、マロンが言いました。マロンの首は、もう動くようになり、振り向いた扉の向こうに、梅雨晴れの空がのぞいていました。「あれ?ゴッツンコは?」「もう、いないわよ」「今日は、僕と僕の思い出のゴッツンコだったんだ」と、マロンが小さな声で言いました。「マロン。私の可愛いマロン」と、思い出のママ犬の声が心の奥の奥に、静かに静かに浸み込んできました。
「あなたが、ママと出会ったときのことを思い出してみて」と、キャサリンが言いました。「ちょうどいい出会いがちょうどいいタイミングであるなんて、不思議だと思わなかった?ちょっとずれただけでも、マロンはママに会えなかったんだし、私とだって出会えなかったのよ」。「マロン。今日、あなたがここにいるのも、ゴッツンコの妖精のおかげなのよ。気づかなかった?」と、キャサリンがあくびをしながら言いました。
「それで、ゴッツンコの妖精って、どこにいるの?」と、マロンは聞きました。「どこにでもいるし、どこにもいないのよ」と、キャサリンは言いました。「ゴッツンコはね。気難し屋さんで、みんなの目にはなかなか見えないけど、ホラ、今、そこにもいたわよ」と、キャサリンがカーテンの陰を指差しました。カーテンは風をはらんで、大きく膨らんで、いかにもゴッツンコの妖精が隠れていそうでした。「ゴッツンコはね、恥ずかしがり屋さんで、みんなのすぐそばにいるけど、決して自分からはいることを知らせないの。だから、ゴッツンコしてみて、初めていたことに気づくのよね」と、キャサリンがベッドの下を指差しました。ベッドの下に何かがもぐりこんで隠れているような気がしました。「このゴッツンコは、僕とキャサリンさんの出会いのゴッツンコなの?」と、マロンは聞きました。「さあ、どうかしら?出会いの前には、私にも分からないわ」と、キャサリンが答えました。
その時、マロンの背後で、入口の扉が音も立てずに開きました。マロンは何かを感じて振り返ろうとしました。でも、マロンの顔は、キャサリンを見つめたまま。しばらくの間は、後を振り返ることができませんでした。マロンは後が気になり、何度も振り返ろうとしましたが、体が言うことを聞いてくれませんでした。「ねえ。キャサリンさん。僕の後ろにいるのは何?ゴッツンコが会わせようとしているのは何なの?」と、マロンが聞きました。「あなたの後にいるのは、誰もが振り返りたくなり、誰もが決して見ることはできないものよ」と、キャサリンが言いました。「えっ?何?」と、マロンは振り返ろうとしました。「それは、あなたの思い出」「僕の思い出?見てみたい」「無理。思い出は振り返って見るものじゃなくて、前を向いているときに背中で感じるものなの。いくら魔女でも、それだけはできないわ。今日のゴッツンコの妖精は、マロンの思い出を連れてきたのね」と、キャサリンが言いました。「見たい。見てみたい」と、マロンはもがきました。でも、マロンの体はますます硬くなり、顔を横に向けることさえできませんでした。
「マロン。静かに目を閉じて感じるのよ。思い出は振り返っても見られないんだから…」と、キャサリンが言いました。マロンは目をつぶりました。マロンの頭の中に、今までに出会った友だちの姿が浮かんできました。ポテトもキャンディーもケロちゃんも、みんなニコニコと笑顔を見せて、マロンの名前を呼んでくれました。「僕のすべての出会いは、ゴッツンコの妖精のしてくれたことなの?」と、マロンは目をつぶったままで聞きました。「そうよ。誰のおかげでもない、妖精たちのおかげよ」と、キャサリンが答えました。マロンの頭の中に、優しいママ犬の笑顔が浮かびました。「ママだ!」と、マロンは叫びました。マロンのママは、ただ黙って笑ってうなずくばかりでした。「ママ!」。マロンは振り返りたい気持ちをぐっと抑えました。「ゴッツンコ。ありがとうね。僕とママを出会わせてくれて」と、マロンがつぶやきました。
「マロン。あなたは本当に幸せよ。だって、思い出のゴッツンコとは、滅多に出会えないもの」と、キャサリンが言いました。「そうなの?」と、マロンが言いました。マロンの首は、もう動くようになり、振り向いた扉の向こうに、梅雨晴れの空がのぞいていました。「あれ?ゴッツンコは?」「もう、いないわよ」「今日は、僕と僕の思い出のゴッツンコだったんだ」と、マロンが小さな声で言いました。「マロン。私の可愛いマロン」と、思い出のママ犬の声が心の奥の奥に、静かに静かに浸み込んできました。