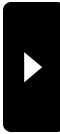2021年08月06日
雨は何の種?
「ねえ、ママ。雨はアサガオの種なの?」と、チカちゃんは聞きました。
ママは少し困って「どうして?」と、聞いてみました。
「だって、雨が降ると、アサガオの芽が出るでしょう?」と、チカちゃんは言いました。
ママは困りました。
「じゃあ、雨は何の種なの?」と、チカちゃんは聞きました。「雨が降ると、カタツムリが生まれるから、雨はカタツムリの種なの?」
「雨は何の種なの?」と、チカちゃんは言いました。「雨が降ると虹が出るから、雨は虹の種なの?」
ママは考えました。「雨は何の種なんだろう?」って。
「ねえ、ママ。雨は何の種?」と、チカちゃんは聞きました。「雨はメダカの種なの?雨が降ると川ができて、メダカが生まれるから、雨はメダカの種だよね?」「雨が降ったら、トマトができたから、雨はトマトの種かな?」
ママは考えました。「雨は何の種なんだろう?」って。
ママは答えました。「チカちゃん、雨は森の種なの。雨が降ると、森では木が生まれて、木が大きくなって、花が咲いて、実がなって、いっぱい、いっぱい深呼吸して、おいしい空気を作ってくれるんだよ」「雨は森の種なの」
チカちゃんは大きく息を吸い込んで、言いました。「雨は森の種なんだよね」
ママは少し困って「どうして?」と、聞いてみました。
「だって、雨が降ると、アサガオの芽が出るでしょう?」と、チカちゃんは言いました。
ママは困りました。
「じゃあ、雨は何の種なの?」と、チカちゃんは聞きました。「雨が降ると、カタツムリが生まれるから、雨はカタツムリの種なの?」
「雨は何の種なの?」と、チカちゃんは言いました。「雨が降ると虹が出るから、雨は虹の種なの?」
ママは考えました。「雨は何の種なんだろう?」って。
「ねえ、ママ。雨は何の種?」と、チカちゃんは聞きました。「雨はメダカの種なの?雨が降ると川ができて、メダカが生まれるから、雨はメダカの種だよね?」「雨が降ったら、トマトができたから、雨はトマトの種かな?」
ママは考えました。「雨は何の種なんだろう?」って。
ママは答えました。「チカちゃん、雨は森の種なの。雨が降ると、森では木が生まれて、木が大きくなって、花が咲いて、実がなって、いっぱい、いっぱい深呼吸して、おいしい空気を作ってくれるんだよ」「雨は森の種なの」
チカちゃんは大きく息を吸い込んで、言いました。「雨は森の種なんだよね」
2021年08月05日
森暮らし始めませんか?
カチャカチャカチャカチャ・・・と、パソコンのキーボードを叩くリスってかなり珍しいのかも知れません。でも、健ちゃんの飼っているシマリスのカリ(♂)とポリ(♀)は、ときどきクルミを抱えるときのように前かがみになって、キーボードに向かっているところを見ます。何をしているのかって?健ちゃんのお父さんがしているところを見ていて、いつの間にかインターネットを覚えてしまったのです。健ちゃんだって、まだできないのに。もちろん、健ちゃんや健ちゃんの家族には内緒ですが・・・。
この頃、カリが関心を持っているのは、森暮らし。都会のマンション暮らしには、そろそろ疲れてきたと言うのです。「何せ、ここに来て、早いものでもう三年目。本当の森なんて知らないし、森のことを知ったのだって、ネットがあればこそ。ネットがなければ、森とか木とか知らなかったわけだけどね。でもね、憧れちゃうよね、森暮らしって」と、言いました。「私たちの仲間って、誰も本当の森を知らないけど、憧れちゃうわよね、森暮らしって」と、ポリも言いました。「ねえ、ネットで調べてみようか?」と、カリが言いました。「賛成」と、ポリが言いました。
二匹は健ちゃんたちの留守をいいことに、パソコンのスイッチをONにしました。ジャーンと音がして、ウィンドウズXPが立ち上がってきます。「これこれ、このデスクトップの背景が森だったんだよね」「そうそう、これで、初めて森を知ったんだもん」。カリは慣れた手つきで、インターネットに接続しました。検索サイトを呼び出して、キーワードを入力しています。「えーと、『森』『環境』『動物』としてみよう」と、カリ。「わー、出てきた、出てきた」と、ポリが喜んでいます。「どこにしようか?」と、カリ。「『野生動物、植物、風景の写真と解説』だって。バーチャル自然公園じゃあ、ダメだよね。本物でなくっちゃ。『森の減少、森林伐採により、すみかを追われる動物たち』だって。これは落ち込んじゃうよね」と、カリが言いました。「そうだね。暗くなっちゃうよね」と、ポリも言いました。「これは、絵本のサイトだし、こっちはNPO自然保護団体のサイトだって」。「これは、どう?」と、カリがマウスを持つ手を止めました。「『森暮らし始めませんか?』。いつかは森暮らしをと望んでいるウサギたちの支援サイトだって。ウサギかあ?でも、ちょっと覗いてみよう」と、カリはカチカチとクリックしました。
しばらくして、ウェブサイトが呼び出されました。トップページは、腕組みをした野ウサギの動画です。「ほう」と、カリは言いました。「ちょっと。ポリ。ドングリを持ってきて」。カリは、健ちゃんのお父さんのマネをして、片手でドングリを抱えて、カリカリやりながら、クリックしています。「もう、ボロボロこぼしてる。そんなところまで、マネしないでよ」と、ポリ。「森の環境をそれぞれ10段階で評価だって。まずは、安全度ポイントだよね」と、カリは言いました。「どこもここも、結構評価が高いわね。8点や9点が多いようだけど。あっ、ここは10点だ。『近くの森』だって。ワシ・タカ類の生存が確認されていず、極めて安全と考えられる」と、ポリが読み上げました。「うーん」と、二匹はうなってしまいました。「つまり、絶滅危惧種ってわけ?でも、森の理想からは遠いね」と、カリは言いました。
「食料自給度だって、大切なポイントだよね。『少し遠くの森』は、近くにニンジンの畑があって、お百姓さんの目を盗めば、食べ放題。罠にかかったウサギの数が、ここ数年激減なんだって。世間では無農薬指向だから、農薬の使用も減っているようだよ。ニンジン?これは、ウサギ向けの情報だから仕方ないか。ドングリはどうなの?クルミはどうなの?知りたいよね?情報ないよね?」と、カリは言いました。「近くに道の駅があって、人間の残飯が食べ放題?これは、プライドが許さないよね。ウサギにプライドはないのか!」。
「えー、森の中には食べ物もたくさんあり、動物たちにとって暮らしやすい環境が整っているのに、どうして森の中から出てきてしまうんだろう、だって?余計なお世話だよね。このウサギはガチガチの自然崇拝だね、きっと。それに僕たちは、森から出てきたんじゃあないしね」と、今度はストローでジュースを飲みながらカリが言いました。
「森のみどり度はどうなの?」と、ポリが尋ねました。「『かなり遠くの森』が、10点だね。でも、行くまでに、危険なところがいっぱいあるよ。トンネルをいくつも通らなくてはいけないし、川を行くにもダムがあって、船では行けそうもないし、ヘビだっているかも知れない。しかも、世界自然遺産だってさ。きっと、僕たちを狙う鳥とか虫とか動物とかがたくさんいるよ。危険なんじゃあない?」と、カリが首を横に振りました。
「次のポイントは何だろう?健康度って?そうか、歯医者さんがいるとか?そうなんだ。この頃、甘い物の食べ過ぎで、虫歯ができちゃったんだ。街に住んでいると、そうなっちゃうよね」と、カリが言いました。「健康度って、森の健康度なんじゃあないの?ほら、人工林なら間伐がされているかとか、日当たりがいいかとか悪いかとか」と、ポリが言いました。
「ねえ?メールで問い合わせを入れてみない?僕たちが暮らすのに理想の森を探してみようよ」と、カリ。「そうね。じゃあ、条件を言うわよ」と、ポリ。「まず、山全部がドングリとかクルミとか実のなる木であること。それも天然ものがいいよね、植林よりも。ドングリだけじゃあ飽きがくるから、フライドチキンなんかも、たまには食べたいよね。あれって、癖になっちゃうから」と、カリが言いました。「あれって、木になるの?私、近くにコンビニが欲しい。チョコとかスナック菓子とか大好きだから。毎日でも食べていたい。ホント言うとドングリよりもね」と、ポリが言いました。「だから、太るんだよ。少し運動でもしたら?」「ヒトのこと言える?ちょとお、タバコの灰が落ちてる!この際だから言っておくけど、TVの大リーグ中継見ながら、寝そべるのはやめてね」「君だって、韓国リスドラマのコリ様とかに夢中じゃあないか!」と、二匹とも、言うことがめちゃくちゃです。
「仲間はどう?知らないリスと一緒に暮らせる?シマリスだけじゃあなくて、ホンドリスとかタイワンリスなんていうのもいるらしいよ」と、カリが尋ねました。「無理、無理。私、わがままだし、知らないリスとのお付き合いなんて、まっぴらだわ。コリ様は別だけど」と、ポリが答えました。「それに、私、夜真っ暗になると眠れないから、明るいところがいいわ」。「そんな森ないよ」と、カリが言いました。「でも、聞いてみて」と、ポリも譲りません。「ITは欠かせないよね」と、カリが言いました。「それこそ、無理に決まっているじゃない。あなたはネットお宅だから」と、ポリはおかんむりです。「じゃあ、社会のことは、どうやって知るの?ライブドアの証券取引法違反事件の行方とか。新聞?テレビ?やっぱりネットでしょう?」と、カリも怒り気味です。「私たちはリスよ。ライブドアなんて関係ないじゃない。ネットをするリスなんて、そうはいないはずよ」「どうして、そんなこと、分かるの?」「じゃあ、『リス』『ネット』のキーワードで検索してみたら?」。
「冬ごもりはするの?」と、カリ。「ただ眠っているだけでしょう?私は絶対にイヤ。冬でも暖かくなくちゃあ。冷暖房は欲しいな。できればお風呂も。半身浴ってダイエットに最適らしいから。それも温泉?やっぱ、天然よね」と、ポリ。もう、わがままの言い放題です。
結局、二匹は『森暮らし始めませんか?』のサイトに、わがままメールを送信しました。
しばらくして、サイトの管理人の野ウサギから返信がありました。「お問い合わせありがとうございました。ご希望の森は、あなたの住んでいるマンション近くの公園です。ここなら、夜も明るく、コンビニも近いし、理想的だと思われます。フライドチキンの店もありますし、缶ジュースの自販機もあります。ただし、夜、放し飼いにされるミニチュアダックスにだけは、注意してください。ただし、森と呼べるかどうか?」と、書いてありました。「犬はまずいよね?」「犬はダメだわ」と、二匹の意見が一致しました。「生意気で、暴力的だし」「そうそう、エサをあげる人以外には、決して服従しようとはしないし、逃げ込む家が欲しいよね」「健ちゃんの家族と暮らすのが一番か?」「私たちを狙う恐ろしい外敵が住む森よりもね」と、虫歯のカリと小太りのポリの二匹のリスは、健ちゃんの家族と暮らし続けることにしました。ポリはクルクルと車を回しながら、「運動もできるしね」と、言いました。「ネットも使い放題だしね」。
この頃、カリが関心を持っているのは、森暮らし。都会のマンション暮らしには、そろそろ疲れてきたと言うのです。「何せ、ここに来て、早いものでもう三年目。本当の森なんて知らないし、森のことを知ったのだって、ネットがあればこそ。ネットがなければ、森とか木とか知らなかったわけだけどね。でもね、憧れちゃうよね、森暮らしって」と、言いました。「私たちの仲間って、誰も本当の森を知らないけど、憧れちゃうわよね、森暮らしって」と、ポリも言いました。「ねえ、ネットで調べてみようか?」と、カリが言いました。「賛成」と、ポリが言いました。
二匹は健ちゃんたちの留守をいいことに、パソコンのスイッチをONにしました。ジャーンと音がして、ウィンドウズXPが立ち上がってきます。「これこれ、このデスクトップの背景が森だったんだよね」「そうそう、これで、初めて森を知ったんだもん」。カリは慣れた手つきで、インターネットに接続しました。検索サイトを呼び出して、キーワードを入力しています。「えーと、『森』『環境』『動物』としてみよう」と、カリ。「わー、出てきた、出てきた」と、ポリが喜んでいます。「どこにしようか?」と、カリ。「『野生動物、植物、風景の写真と解説』だって。バーチャル自然公園じゃあ、ダメだよね。本物でなくっちゃ。『森の減少、森林伐採により、すみかを追われる動物たち』だって。これは落ち込んじゃうよね」と、カリが言いました。「そうだね。暗くなっちゃうよね」と、ポリも言いました。「これは、絵本のサイトだし、こっちはNPO自然保護団体のサイトだって」。「これは、どう?」と、カリがマウスを持つ手を止めました。「『森暮らし始めませんか?』。いつかは森暮らしをと望んでいるウサギたちの支援サイトだって。ウサギかあ?でも、ちょっと覗いてみよう」と、カリはカチカチとクリックしました。
しばらくして、ウェブサイトが呼び出されました。トップページは、腕組みをした野ウサギの動画です。「ほう」と、カリは言いました。「ちょっと。ポリ。ドングリを持ってきて」。カリは、健ちゃんのお父さんのマネをして、片手でドングリを抱えて、カリカリやりながら、クリックしています。「もう、ボロボロこぼしてる。そんなところまで、マネしないでよ」と、ポリ。「森の環境をそれぞれ10段階で評価だって。まずは、安全度ポイントだよね」と、カリは言いました。「どこもここも、結構評価が高いわね。8点や9点が多いようだけど。あっ、ここは10点だ。『近くの森』だって。ワシ・タカ類の生存が確認されていず、極めて安全と考えられる」と、ポリが読み上げました。「うーん」と、二匹はうなってしまいました。「つまり、絶滅危惧種ってわけ?でも、森の理想からは遠いね」と、カリは言いました。
「食料自給度だって、大切なポイントだよね。『少し遠くの森』は、近くにニンジンの畑があって、お百姓さんの目を盗めば、食べ放題。罠にかかったウサギの数が、ここ数年激減なんだって。世間では無農薬指向だから、農薬の使用も減っているようだよ。ニンジン?これは、ウサギ向けの情報だから仕方ないか。ドングリはどうなの?クルミはどうなの?知りたいよね?情報ないよね?」と、カリは言いました。「近くに道の駅があって、人間の残飯が食べ放題?これは、プライドが許さないよね。ウサギにプライドはないのか!」。
「えー、森の中には食べ物もたくさんあり、動物たちにとって暮らしやすい環境が整っているのに、どうして森の中から出てきてしまうんだろう、だって?余計なお世話だよね。このウサギはガチガチの自然崇拝だね、きっと。それに僕たちは、森から出てきたんじゃあないしね」と、今度はストローでジュースを飲みながらカリが言いました。
「森のみどり度はどうなの?」と、ポリが尋ねました。「『かなり遠くの森』が、10点だね。でも、行くまでに、危険なところがいっぱいあるよ。トンネルをいくつも通らなくてはいけないし、川を行くにもダムがあって、船では行けそうもないし、ヘビだっているかも知れない。しかも、世界自然遺産だってさ。きっと、僕たちを狙う鳥とか虫とか動物とかがたくさんいるよ。危険なんじゃあない?」と、カリが首を横に振りました。
「次のポイントは何だろう?健康度って?そうか、歯医者さんがいるとか?そうなんだ。この頃、甘い物の食べ過ぎで、虫歯ができちゃったんだ。街に住んでいると、そうなっちゃうよね」と、カリが言いました。「健康度って、森の健康度なんじゃあないの?ほら、人工林なら間伐がされているかとか、日当たりがいいかとか悪いかとか」と、ポリが言いました。
「ねえ?メールで問い合わせを入れてみない?僕たちが暮らすのに理想の森を探してみようよ」と、カリ。「そうね。じゃあ、条件を言うわよ」と、ポリ。「まず、山全部がドングリとかクルミとか実のなる木であること。それも天然ものがいいよね、植林よりも。ドングリだけじゃあ飽きがくるから、フライドチキンなんかも、たまには食べたいよね。あれって、癖になっちゃうから」と、カリが言いました。「あれって、木になるの?私、近くにコンビニが欲しい。チョコとかスナック菓子とか大好きだから。毎日でも食べていたい。ホント言うとドングリよりもね」と、ポリが言いました。「だから、太るんだよ。少し運動でもしたら?」「ヒトのこと言える?ちょとお、タバコの灰が落ちてる!この際だから言っておくけど、TVの大リーグ中継見ながら、寝そべるのはやめてね」「君だって、韓国リスドラマのコリ様とかに夢中じゃあないか!」と、二匹とも、言うことがめちゃくちゃです。
「仲間はどう?知らないリスと一緒に暮らせる?シマリスだけじゃあなくて、ホンドリスとかタイワンリスなんていうのもいるらしいよ」と、カリが尋ねました。「無理、無理。私、わがままだし、知らないリスとのお付き合いなんて、まっぴらだわ。コリ様は別だけど」と、ポリが答えました。「それに、私、夜真っ暗になると眠れないから、明るいところがいいわ」。「そんな森ないよ」と、カリが言いました。「でも、聞いてみて」と、ポリも譲りません。「ITは欠かせないよね」と、カリが言いました。「それこそ、無理に決まっているじゃない。あなたはネットお宅だから」と、ポリはおかんむりです。「じゃあ、社会のことは、どうやって知るの?ライブドアの証券取引法違反事件の行方とか。新聞?テレビ?やっぱりネットでしょう?」と、カリも怒り気味です。「私たちはリスよ。ライブドアなんて関係ないじゃない。ネットをするリスなんて、そうはいないはずよ」「どうして、そんなこと、分かるの?」「じゃあ、『リス』『ネット』のキーワードで検索してみたら?」。
「冬ごもりはするの?」と、カリ。「ただ眠っているだけでしょう?私は絶対にイヤ。冬でも暖かくなくちゃあ。冷暖房は欲しいな。できればお風呂も。半身浴ってダイエットに最適らしいから。それも温泉?やっぱ、天然よね」と、ポリ。もう、わがままの言い放題です。
結局、二匹は『森暮らし始めませんか?』のサイトに、わがままメールを送信しました。
しばらくして、サイトの管理人の野ウサギから返信がありました。「お問い合わせありがとうございました。ご希望の森は、あなたの住んでいるマンション近くの公園です。ここなら、夜も明るく、コンビニも近いし、理想的だと思われます。フライドチキンの店もありますし、缶ジュースの自販機もあります。ただし、夜、放し飼いにされるミニチュアダックスにだけは、注意してください。ただし、森と呼べるかどうか?」と、書いてありました。「犬はまずいよね?」「犬はダメだわ」と、二匹の意見が一致しました。「生意気で、暴力的だし」「そうそう、エサをあげる人以外には、決して服従しようとはしないし、逃げ込む家が欲しいよね」「健ちゃんの家族と暮らすのが一番か?」「私たちを狙う恐ろしい外敵が住む森よりもね」と、虫歯のカリと小太りのポリの二匹のリスは、健ちゃんの家族と暮らし続けることにしました。ポリはクルクルと車を回しながら、「運動もできるしね」と、言いました。「ネットも使い放題だしね」。
2021年08月04日
窓から森がやって来た
開け放した窓から、ニュウっと森が入ってくるのを見たことがある人は多いのではないでしょうか?
幸ちゃんも、夏の晴れた朝、窓辺のカーテンを膨らませて、森が入ってくるところを見ていたのです。「お母さん、森が入ってきた。ねえ、お母さん、今ね、森がね・・・」と、叫んだのですが、お母さんは「風が入るのよ」と言って、取り合ってくれません。幸ちゃんは「ううん。私は、森が入ってくるのを、今までに何度も見ているのよ。あれは、風じゃあなくて、森が入って来ているに違いないわ。今だって、ほら、森が入って来ている」と、言い張りました。
「だって、セミがあんなに大きな声で鳴いているのも、近くに森が来ているからだわ。それに、チョウだってトンボだって、こんなに飛んでる。今、緑の匂いがいっぱいになってね、森がニュウっと入って来たの」。幸ちゃんは、風邪でもひいてしまったのか、少し熱が出てしまい、二階の自分の部屋のベッドに横になったまま、外の景色を眺めていました。隣の屋根越しに、真夏の青空が広がり、白い雲があっちにポカリ、こっちにポカリと浮かび、入道雲の卵みたいな雲がラジオ体操でもしているように、両手を天に突き上げています。「つまんないな。熱さえ下がれば、公園に行けたのに」と、残念そうです。カーテンが膨らんでいます。何度も何度もひるがえっては、また膨らんでいます。「風なんかじゃあないわよ。風だったら、あんなに膨らむわけないわ。耳を澄ませば小鳥の声だって聞こえるし、川のせせらぎの音だって聞こえる。きっと、妹とドングリの苗を植えに行った、あの森だわ。あの森と同じ匂いがする。そうよ、きっとそうよ。森が私のところまで来てくれたんだわ」と、独り言みたいにつぶやきました。
ドングリの苗は、幸ちゃんがドングリの実から育てたもの。鉢に土を入れ、真ん中辺りを指で押してくぼみを作り、ボランティアリーダーさんからいただいたドングリの実を「早く大きくなーれ!」と唱えながら、一粒埋めました。それから、毎日毎日水をあげ、芽の先っぽを見つけたときの嬉しさは、忘れられない思い出です。雨の日もあり、風の強い日もあり、真夏の日差しがこれでもかと照りつける日もありました。次第に幹を伸ばし、一枚また一枚と葉の数を増やし、幸ちゃんによく似て少し痩せっぽちでしたが、やがて森へと返す日がやって来ました。
幸ちゃんが森を初めて感じたのは、森の入口でバスから降りたときのことでした。緑の香りと一緒に味わった、何とも言えないあの感じ。空気を思いっきり吸い込むと、空気に混じって、森が体の中の中まで入って来たような気がしたのです。クネクネ曲がりくねった山道をバスに乗ってきた幸ちゃんは、少し気分が悪くなってしまったのですが、降り立った途端に味わった森の空気のおいしさに、思わず両手を合わせて「感謝、感謝。森に感謝」と、体調はすっかり元の通り。それどころか、森の斜面に足を踏ん張り、元気いっぱい痩せっぽちのドングリの苗木を植えることができました。両手ですくって飲んだ森の水の冷たさおいしさも忘れられません。その帰り道、木の葉を揺らす風の音に混じって「幸ちゃん、ありがとう」と話す低くて太い声が、幸ちゃんの背中の方からいつまでも追いかけて来ているような気がしました。「森の声だわ」と、幸ちゃんは思いました。
そのあと、近くに森を感じることが何度かありました。大好きな一輪車に乗って近くの公園まで行ったときには、「幸ちゃん、遊ぼう」と、あの低くて太い声が聞こえ、背中をグングン押してくれるのを感じました。「ありがとう。でも、ちょっと怖いから、もう押さないで」と、言ったら今度は前に回って、手を引いてくれました。いつも、フラフラ走る幸ちゃんの一輪車も、そのときだけはスイスイと走り、友だちをみんな置いてきぼりにしてしまいました。森の香りを感じ、森の声を聞きました。森のやさしさを知り、森の力強さを知りました。
公園では、新しいドングリの実をたくさん拾いました。「森からのプレゼントだわ」と、幸ちゃんは思いました。幸ちゃんは、今年も苗を育てています。ドングリは「僕はいつになったら大きくなるの?」と、聞いてきます。「まだまだ。長い長い時間が必要なのよ」と、話しかけながらジョロで水をあげています。ドングリの鉢の横には、トマトの苗も一本植えました。今、緑色のトマトの赤ちゃんが、少し赤みを帯びてきています。「もうすぐ、真っ赤になったら、食べさせてもらうからね」と、幸ちゃんはトマトにも話しかけています。「でも、森はすぐには大人になれないのよ。友だちも必要だし、仲間だって欲しいのよ」。
校庭でブランコ遊びをしているときにも、森がすぐそばに来ているのを感じました。幸ちゃんの体は森に包まれて、前に後ろにユラリユラリと大きく揺れました。「そんなに揺すって、怖くないの?」と、友だちが心配顔で眺めていました。「ううん。全然怖くないわ。だって、私が揺すっているんじゃあないし、私は、今、森の太い腕に抱かれているんだもの」と、幸ちゃんは言いました。
国語の授業中には、教科書をペラペラめくって、ちょっぴりいたずらもされました。「そこにいてもいいけど、おとなしくしていて。いたずらは止めて」と、幸ちゃんは小声で言いました。教科書は宮沢賢治の『風の又三郎』のページを開いてピタリと止まりました。
体育の時間は、苦手の鉄棒の練習でした。どうしてもお尻が上がらなかった逆上がりが、その日はスイスイとできました。「幸子、すごいじゃあないか」と、先生がビックリしています。もちろん、幸ちゃんも驚いたのですが、このときも森の太い腕が、幸ちゃんの体を持ち上げてくれたのを感じていました。「サンキュー!」と、幸ちゃんは言いました。
そんなことが何度もあったので、窓辺から森が入ってきても、不思議とも感じませんでした。「お母さんは信じてくれないけど、そこにいるのよね」と、森に話しかけました。「わー、涼しい。あの森に行ったときと同じだわ。「私ね。公園に行きたいの」と、言ってみました。「公園には、木がたくさん植えられていてね。そんな木の木陰で眠るのが最高なの。ねえ、公園に連れて行って」と、お願いしてみました。森の太い腕に包まれたかと思おうと、幸ちゃんの体はフワリと宙に浮きました。気がつくと、大きく開いた窓から泳ぐように漂い出ていました。「お母さんが洗濯物を干しているわ。お母さーん」。幸ちゃんは高い所から見下ろしていたのですが、お母さんは幸ちゃんに気づきませんでした。洗濯物が風に大きくそよぎました。「ああ、健ちゃんが一輪車に乗っている。きっと公園に行くんだわ」と、思いました。「背中を押してやって」と、森にお願いしました。健ちゃんの一輪車のスピードがグングン上がりました。健ちゃんは首をひねりながら、少し慌てています。「ダメダメ。横断歩道では止めてあげて」と、幸ちゃんは言いました。健ちゃんの一輪車はピタリと止まりました。
公園では、妹たちがチョウを追いかけていました。「ねえ、チョウをいっぱい集められない?」と、お願いしてみました。すると、どうでしょう。辺りは、青や黄色、赤の美しいチョウたちがたくさん集まってきました。ヒラヒラヒラヒラと妹たちの頭の上を舞い始めました。妹たちは、少し驚いた様子でしたが、チョウと一緒に踊り始めました。「わー、楽しそう。私も早く元気になって、公園で遊びたいな」と、言いました。
次の瞬間、幸ちゃんは自分の部屋のベッドの上でした。森はまだ部屋の中にいました。ほてった体を、森の風が心地よく吹き抜けました。小鳥のさえずりが聞こえました。小川のせせらぎの音も響きました。
セミの鳴く大声で目が覚めました。窓辺のカーテンが大きく大きく膨らんでいました。お母さんがやってきました。「ねえ、お母さん、森が入ってきている」と、幸ちゃんは言いました。「そうなの?」と、幸ちゃんの額に手を当てました。「あら?熱が下がっている。幸子のトマトが、美味しそうに真っ赤に色づいていたわよ」と、お母さんが言いました。「早いね。トマトは、もう大人になったんだ。ねえ、お母さん。私、ドングリの木に水をあげなくちゃあね。森はなかなか大人になれないから」。「ねえ、お母さん、森がね。窓からニュウと入ってきたの」と、幸ちゃんが嬉しそうに言いました。
幸ちゃんも、夏の晴れた朝、窓辺のカーテンを膨らませて、森が入ってくるところを見ていたのです。「お母さん、森が入ってきた。ねえ、お母さん、今ね、森がね・・・」と、叫んだのですが、お母さんは「風が入るのよ」と言って、取り合ってくれません。幸ちゃんは「ううん。私は、森が入ってくるのを、今までに何度も見ているのよ。あれは、風じゃあなくて、森が入って来ているに違いないわ。今だって、ほら、森が入って来ている」と、言い張りました。
「だって、セミがあんなに大きな声で鳴いているのも、近くに森が来ているからだわ。それに、チョウだってトンボだって、こんなに飛んでる。今、緑の匂いがいっぱいになってね、森がニュウっと入って来たの」。幸ちゃんは、風邪でもひいてしまったのか、少し熱が出てしまい、二階の自分の部屋のベッドに横になったまま、外の景色を眺めていました。隣の屋根越しに、真夏の青空が広がり、白い雲があっちにポカリ、こっちにポカリと浮かび、入道雲の卵みたいな雲がラジオ体操でもしているように、両手を天に突き上げています。「つまんないな。熱さえ下がれば、公園に行けたのに」と、残念そうです。カーテンが膨らんでいます。何度も何度もひるがえっては、また膨らんでいます。「風なんかじゃあないわよ。風だったら、あんなに膨らむわけないわ。耳を澄ませば小鳥の声だって聞こえるし、川のせせらぎの音だって聞こえる。きっと、妹とドングリの苗を植えに行った、あの森だわ。あの森と同じ匂いがする。そうよ、きっとそうよ。森が私のところまで来てくれたんだわ」と、独り言みたいにつぶやきました。
ドングリの苗は、幸ちゃんがドングリの実から育てたもの。鉢に土を入れ、真ん中辺りを指で押してくぼみを作り、ボランティアリーダーさんからいただいたドングリの実を「早く大きくなーれ!」と唱えながら、一粒埋めました。それから、毎日毎日水をあげ、芽の先っぽを見つけたときの嬉しさは、忘れられない思い出です。雨の日もあり、風の強い日もあり、真夏の日差しがこれでもかと照りつける日もありました。次第に幹を伸ばし、一枚また一枚と葉の数を増やし、幸ちゃんによく似て少し痩せっぽちでしたが、やがて森へと返す日がやって来ました。
幸ちゃんが森を初めて感じたのは、森の入口でバスから降りたときのことでした。緑の香りと一緒に味わった、何とも言えないあの感じ。空気を思いっきり吸い込むと、空気に混じって、森が体の中の中まで入って来たような気がしたのです。クネクネ曲がりくねった山道をバスに乗ってきた幸ちゃんは、少し気分が悪くなってしまったのですが、降り立った途端に味わった森の空気のおいしさに、思わず両手を合わせて「感謝、感謝。森に感謝」と、体調はすっかり元の通り。それどころか、森の斜面に足を踏ん張り、元気いっぱい痩せっぽちのドングリの苗木を植えることができました。両手ですくって飲んだ森の水の冷たさおいしさも忘れられません。その帰り道、木の葉を揺らす風の音に混じって「幸ちゃん、ありがとう」と話す低くて太い声が、幸ちゃんの背中の方からいつまでも追いかけて来ているような気がしました。「森の声だわ」と、幸ちゃんは思いました。
そのあと、近くに森を感じることが何度かありました。大好きな一輪車に乗って近くの公園まで行ったときには、「幸ちゃん、遊ぼう」と、あの低くて太い声が聞こえ、背中をグングン押してくれるのを感じました。「ありがとう。でも、ちょっと怖いから、もう押さないで」と、言ったら今度は前に回って、手を引いてくれました。いつも、フラフラ走る幸ちゃんの一輪車も、そのときだけはスイスイと走り、友だちをみんな置いてきぼりにしてしまいました。森の香りを感じ、森の声を聞きました。森のやさしさを知り、森の力強さを知りました。
公園では、新しいドングリの実をたくさん拾いました。「森からのプレゼントだわ」と、幸ちゃんは思いました。幸ちゃんは、今年も苗を育てています。ドングリは「僕はいつになったら大きくなるの?」と、聞いてきます。「まだまだ。長い長い時間が必要なのよ」と、話しかけながらジョロで水をあげています。ドングリの鉢の横には、トマトの苗も一本植えました。今、緑色のトマトの赤ちゃんが、少し赤みを帯びてきています。「もうすぐ、真っ赤になったら、食べさせてもらうからね」と、幸ちゃんはトマトにも話しかけています。「でも、森はすぐには大人になれないのよ。友だちも必要だし、仲間だって欲しいのよ」。
校庭でブランコ遊びをしているときにも、森がすぐそばに来ているのを感じました。幸ちゃんの体は森に包まれて、前に後ろにユラリユラリと大きく揺れました。「そんなに揺すって、怖くないの?」と、友だちが心配顔で眺めていました。「ううん。全然怖くないわ。だって、私が揺すっているんじゃあないし、私は、今、森の太い腕に抱かれているんだもの」と、幸ちゃんは言いました。
国語の授業中には、教科書をペラペラめくって、ちょっぴりいたずらもされました。「そこにいてもいいけど、おとなしくしていて。いたずらは止めて」と、幸ちゃんは小声で言いました。教科書は宮沢賢治の『風の又三郎』のページを開いてピタリと止まりました。
体育の時間は、苦手の鉄棒の練習でした。どうしてもお尻が上がらなかった逆上がりが、その日はスイスイとできました。「幸子、すごいじゃあないか」と、先生がビックリしています。もちろん、幸ちゃんも驚いたのですが、このときも森の太い腕が、幸ちゃんの体を持ち上げてくれたのを感じていました。「サンキュー!」と、幸ちゃんは言いました。
そんなことが何度もあったので、窓辺から森が入ってきても、不思議とも感じませんでした。「お母さんは信じてくれないけど、そこにいるのよね」と、森に話しかけました。「わー、涼しい。あの森に行ったときと同じだわ。「私ね。公園に行きたいの」と、言ってみました。「公園には、木がたくさん植えられていてね。そんな木の木陰で眠るのが最高なの。ねえ、公園に連れて行って」と、お願いしてみました。森の太い腕に包まれたかと思おうと、幸ちゃんの体はフワリと宙に浮きました。気がつくと、大きく開いた窓から泳ぐように漂い出ていました。「お母さんが洗濯物を干しているわ。お母さーん」。幸ちゃんは高い所から見下ろしていたのですが、お母さんは幸ちゃんに気づきませんでした。洗濯物が風に大きくそよぎました。「ああ、健ちゃんが一輪車に乗っている。きっと公園に行くんだわ」と、思いました。「背中を押してやって」と、森にお願いしました。健ちゃんの一輪車のスピードがグングン上がりました。健ちゃんは首をひねりながら、少し慌てています。「ダメダメ。横断歩道では止めてあげて」と、幸ちゃんは言いました。健ちゃんの一輪車はピタリと止まりました。
公園では、妹たちがチョウを追いかけていました。「ねえ、チョウをいっぱい集められない?」と、お願いしてみました。すると、どうでしょう。辺りは、青や黄色、赤の美しいチョウたちがたくさん集まってきました。ヒラヒラヒラヒラと妹たちの頭の上を舞い始めました。妹たちは、少し驚いた様子でしたが、チョウと一緒に踊り始めました。「わー、楽しそう。私も早く元気になって、公園で遊びたいな」と、言いました。
次の瞬間、幸ちゃんは自分の部屋のベッドの上でした。森はまだ部屋の中にいました。ほてった体を、森の風が心地よく吹き抜けました。小鳥のさえずりが聞こえました。小川のせせらぎの音も響きました。
セミの鳴く大声で目が覚めました。窓辺のカーテンが大きく大きく膨らんでいました。お母さんがやってきました。「ねえ、お母さん、森が入ってきている」と、幸ちゃんは言いました。「そうなの?」と、幸ちゃんの額に手を当てました。「あら?熱が下がっている。幸子のトマトが、美味しそうに真っ赤に色づいていたわよ」と、お母さんが言いました。「早いね。トマトは、もう大人になったんだ。ねえ、お母さん。私、ドングリの木に水をあげなくちゃあね。森はなかなか大人になれないから」。「ねえ、お母さん、森がね。窓からニュウと入ってきたの」と、幸ちゃんが嬉しそうに言いました。
2021年08月03日
ランラン森気分
『商品番号0000 ランラン森気分 あなたに森の緑をお届けします。価格0円』。幸ちゃんが、その紙切れを見つけたのは、お母さんがペラペラとめくっていた通信販売カタログの最後のページでした。「なんて下手な字かしら。私だって、もう少しマシな字を書けるのに」。カタログに印刷されているわけではありませんので、誰かが挟んだのか、紛れ込んだのでしょう。「それに、これって何の絵?森?」。そこには、クレヨンで描きなぐったような下手くそな森の絵が添えられていました。それでも、森の絵だと分かったのには理由があります。使われているクレヨンの色は、みどり、きみどり、あおみどり、あとは名前も知らない色ばかりですが、まるで緑一色。「これは、きっと森の絵のつもりね?」と、納得するしかなかったのです。
ピンポーン。夏休みのある日、玄関に宅配便が届きました。通信販売の荷物でした。早速、お母さんが開けています。幸ちゃんも興味しんしん、覗き込みました。「あれっ?これは何かしら?」と、お母さんが小さな箱を取り出しました。下手な字で『ランラン森気分』と書いてありました。「ああ、これって、私が頼んだんだわ。誰かのいたずらかと思ってた。本当は忘れてしまっていたけどね」と、幸ちゃんが思い出しました。「何が入っているのかしら?」と、その小さな箱をそーっと開いてみました。
中には、ヒノキ、スギ、ケヤキ、カエデ、クス・・・森の木、木、木、木の名前ついた緑色のクレヨンがぎっしりと詰められていました。「何て変なクレヨン。木の名前がついているだけだし、緑色ばかりじゃあない」と、幸ちゃんは思いました。「それにしても、いい匂い」と、幸ちゃんは言いました。「描いてみようっと」。
幸ちゃんはチラシの裏に木の葉の絵を描きました。「わあ、いい匂い。ヒノキだわ。きっと、このクレヨンに何か入っているのよね」と、幸ちゃんは思いました。その匂いはヒノキの香りです。森の香りです。「こっちはカシだって」と、今度は別のクレヨンでお絵描きです。「わー、これもいい匂い。でも、少し匂いが違ってる」と、幸ちゃんは思いました。
幸ちゃんのお絵描きは続きます。木の名前のついたクレヨンで、次々とお母さんの顔、友達の顔、犬や花、お菓子・・・と、何を描いても、森にしか見えません。「だって、全部緑なんだもん。仕方ないよね。でも、いい匂いだから、まあいいか」。
それにしても、きれいな緑です。「なるほど、『ランラン森気分』って言うだけのことはあるわね。誰が描いても下手に描いても何を描いても、これなら森に見えるわね」と、幸ちゃんは感心しました。なんだか、自分が森の中に入っているような、いい気分になってきました。緑の葉が茂る森の小道を歩いてズンズン行くと、小川があったり池があったり、小鳥が飛んでいたり、さえずっていたり。「ステキね。なんだか、森の動物たちにも出会えそうね。こんな気持ちが森気分って言うのかしら」と、幸ちゃんはつぶやきました。
幸ちゃんは、まだまだ描いています。お母さんが冷たく冷えたジュースを持ってきました。「まだ描いてるの?もういい加減にしたら?」。夢中になっている幸ちゃんに言いました。「本当に木が生えてきたら、どうするつもり?」と、お母さんが止めました。「まさか?大丈夫、大丈夫。でも、本当にそうなったらもっとステキね。」と、幸ちゃんは言いました。
ピンポーン。そのとき、玄関のチャイムが鳴りました。玄関にいたのは野ウサギと野ネズミの二匹です。「ごめんください」と、野ウサギが言いました。「ごめんください」と、野ネズミも続けました。「ええ?家を間違えていませんか?」と、ドアを開けたお母さんが応じました。「いえ。突然ですが、こちらに森があると聞きまして、寄らせていただきました。」と、野ウサギが丁寧に話しました。「僕たち、森がないと、暮らせないものですから」と、野ネズミもお願いしました。二匹はドンドン部屋の中に入ってきました。「ああ、ここだ、ここだ。この森で暮らしたいと思いまして」と、野ウサギが言いました。幸ちゃんは、あきれています。「だって、これは森の絵でしょう?しかも、本当は森の絵でなんかじゃあなくて、これがお母さんで、これがお菓子。でも、緑一色だから、森みたいになってしまったの」。「いえ。すばらしい森です」と、野ウサギは言いました。「では、失礼します」と、野ネズミが言ったかと思うと、二匹の姿は見えなくなり、どこかに消えてしまいました。
二匹は絵の森の中にいました。「やあ、やあ。いい森だ。ヒノキ、スギ、ケヤキ、クス、カシ・・・。近頃では、こんなに木が育った森はなかなか見つけられないよ」と、野ウサギが言いました。「まさに、『ランラン森気分』だね」と、野ネズミが応じました。「人間って、本当は森が好きなんだね」「そうさ。木も森も大好きさ。だけど、どうして、森を荒らしてしまったんだろう?」「どうして、森を荒らしてしまったんだろう?」二匹は、腕組みをして首をひねりました。「もう、本当の森なんて、どこにもないんだから」と、野ウサギが嘆きました。「もう、本当の森なんて、どこにもないよね」と、野ネズミが応じました。
幸ちゃんは、まだまだお絵描きを続けました。そのたびに、絵の森では新しい木がニョキと生えてきます。一本、また一本。クレヨンを変えると、木も変わります。「最高だね!」と、野ネズミが言いました。「幸ちゃん、もっと描いてね」と、野ネズミは精一杯大きな声を出しました。幸ちゃんには、何か小さな声で「森を守ってね」と、言っているのが聞こえたような気がしました。「木や自然を大切にね」と、言っているような気もしました。
ピンポーン。チャイムが鳴りました。玄関には、イノシシの親子とリスがいました。「まあ、今度はイノシシとリスなの?」と、お母さんがあきれて言いました。「失礼します」と言いながら、三匹はドンドン入ってきました。「この子が熱を出しているの。森にいるのが一番の治療だから、お願いします。こちらの森は最高だと聞きましたので・・・」と、お母さんイノシシが頼みました。「虫歯になってしまったんです。痛くて、痛くて、こんなに腫れているんです。こちらの森には、いい歯医者さんがいるって聞きましたので」と、リスも頼みました。「え?歯医者さん?」は、幸ちゃんは不思議そうな顔をしました。そのとき、絵の森の中から、さきほどの野ウサギが顔を出しました。「ああ、幸ちゃん、僕のことです。じゃあ、ちょっと見せてもらおうか?」と、言いながら、野ウサギとイノシシの親子とリスは、絵の森の中に消えていきました。
森の中では、お母さんイノシシが「風も涼しいし、木も茂って、ステキな森ね。これなら、うちの坊やもすぐに直りそう」と、ほっと一息つきました。リスは大きな口を開けて、野ウサギの治療を受けていますので話せませんでしたが、大きく一つうなずきました。「こんなにステキな森は、もうどこにもありませんね」と、お母さんイノシシは言いました。リスは痛みをこらえていますので話せませんでしたが、力強くうなずきました。
ピンポーン。「ほら、またお客さんよ」と、幸ちゃんは言いました。「今度は誰なの?」。「森林環境研究所の者です」と、自己紹介をしたのは、サルとクマでした。「もう、勝手にして」と、幸ちゃんは思いました。「こちらの森の二酸化炭素吸収率が極めて高いと聞いたものですから、調査に伺いました。地球温暖化対策を進める京都議定書で、我が国は二酸化炭素など温室効果ガスを1990年比で6%削減することを義務付けられているのです」と、舌をかみそうになりながらサルが言いました。「こちらの森の京都議定書達成に向けての積極的な取り組みが・・・」と、クマが言いかけたとき、「『こちらの森』とか、言うのやめていただけませんか?うちには本当の森なんてありませんし、この絵だって下手くそかも知れないけど、お母さんの顔やお菓子を描いたものなんです」と、幸ちゃんはさえぎりましたが、二匹は絵の森の中に消えてしまいました。
サルは奇妙な器械を取り出して、森の空気を測りました。「うーん。最高の環境だ。木は光合成をすることで二酸化炭素を吸収して炭素を取り込んで育ち、吸収量は木の重量に比例するんだ」と、研究所員らしく言いました。クマは大きく深呼吸をして、森の空気を味わいました。「うーん。『ランラン森気分』最高の味だ。ハチミツの匂いもするぞ」と、舌なめずりをしました。
「人間って、本当は森が好きなんだね」「そうさ。木も森も大好きさ。だけど、どうして、森を荒らしてしまったんだろう?」「どうして、森を荒らしてしまったんだろう?」。野ウサギも野ネズミもイノシシの親子もリスもサルもクマも、全員が腕を組んで首をひねりました。「そうだ」と、野ウサギが提案しました。「僕たちも、森の絵を描いてあげよう。幸ちゃんたちが森の暮らしを楽しめるようにさ」。野ウサギも野ネズミもイノシシの親子もリスもサルもクマも、全員で森の絵を描きました。緑、緑、緑一色のクレヨンでヒノキやスギやケヤキやカエデやクス・・・、木や葉っぱやクルクルやグチャグチャやヘンテコリンやメチャクチャや、それでも、なぜか森に見える絵を描きました。絵の森では、木がもっともっとたくさん生えてきました。
「さあ、幸ちゃんを迎えにいこう」。野ウサギが幸ちゃんを迎えにいきました。「幸ちゃん、僕たちの森に遊びに来ない?」と、野ウサギが誘いました。幸ちゃんは少し考えて「うん、連れて行ってもらうわ」と、答えました。「じゃあ、ちょっとだけ目をつぶって」。
遠くで叫ぶ幸ちゃんの声が、絵の森の中から聞こえてきました。「ねえ。お母さん。本当の木が生えているよ。何本も何本も生えているよ」と、言っているように聞こえました。「やったー!これで、幸ちゃんも森の恵みを味わえるね」「よかったね」と、絵の森の中では、野ウサギも野ネズミもイノシシの親子もリスもサルもクマも、みんな大喜びでした。イノシシの坊やもすっかり元気になっていました。虫歯のリスも、もうニコニコ顔です。木々の葉は風にそよぎ、いつの間にか小鳥たちも舞っています。幸ちゃんは、思いっきり深呼吸して、森の空気をいっぱい吸い込みました。森林環境研究所員のサルが「我が国の森林の約40%を占める人工林は、外材の輸入増加等による林業の不振で、間伐などの手入れが行われにくくなっています。このままでは水を貯める力も土砂崩れを防ぐ力も失われてしまします」と、生意気そうに力説しました。「まあまあ、それも大切な話かもしれないけど、幸ちゃん、『ランラン森気分』だね」と、クマが言いました。「そうそう、それも大事な話かもしれないけど、『ランラン森気分』だわ」と、幸ちゃんも応えました。「ところで、あのクレヨンって、何だったのかしら?」と、幸ちゃんが尋ねました。「ああ、あれは僕の発明です」と、野ネズミが答えました。「あの、下手くそな絵は?」「あれはイノシシの坊やの絵です。僕は森の発明家だし、イノシシ坊やは画家の卵です。ステキでしょう?」と、野ネズミは続けました。「ときどき遊びに来てもいいかしら?」「もちろん。大歓迎さ」と、みんな声をそろえて言いました。幸ちゃんは、「森の緑もステキ。森の仲間もステキ。森って最高!」と、両手を突き上げて叫びました。
お母さんもニコニコしながら、大きな声で呼びました。「幸ちゃーん、夕ご飯の時間ですよー。帰ってらっしゃーい!」。「ハーイ」。絵の森の中からは「ランランラン♪森きぶ~ん♪」の大合唱が聞こえてきました。
ピンポーン。夏休みのある日、玄関に宅配便が届きました。通信販売の荷物でした。早速、お母さんが開けています。幸ちゃんも興味しんしん、覗き込みました。「あれっ?これは何かしら?」と、お母さんが小さな箱を取り出しました。下手な字で『ランラン森気分』と書いてありました。「ああ、これって、私が頼んだんだわ。誰かのいたずらかと思ってた。本当は忘れてしまっていたけどね」と、幸ちゃんが思い出しました。「何が入っているのかしら?」と、その小さな箱をそーっと開いてみました。
中には、ヒノキ、スギ、ケヤキ、カエデ、クス・・・森の木、木、木、木の名前ついた緑色のクレヨンがぎっしりと詰められていました。「何て変なクレヨン。木の名前がついているだけだし、緑色ばかりじゃあない」と、幸ちゃんは思いました。「それにしても、いい匂い」と、幸ちゃんは言いました。「描いてみようっと」。
幸ちゃんはチラシの裏に木の葉の絵を描きました。「わあ、いい匂い。ヒノキだわ。きっと、このクレヨンに何か入っているのよね」と、幸ちゃんは思いました。その匂いはヒノキの香りです。森の香りです。「こっちはカシだって」と、今度は別のクレヨンでお絵描きです。「わー、これもいい匂い。でも、少し匂いが違ってる」と、幸ちゃんは思いました。
幸ちゃんのお絵描きは続きます。木の名前のついたクレヨンで、次々とお母さんの顔、友達の顔、犬や花、お菓子・・・と、何を描いても、森にしか見えません。「だって、全部緑なんだもん。仕方ないよね。でも、いい匂いだから、まあいいか」。
それにしても、きれいな緑です。「なるほど、『ランラン森気分』って言うだけのことはあるわね。誰が描いても下手に描いても何を描いても、これなら森に見えるわね」と、幸ちゃんは感心しました。なんだか、自分が森の中に入っているような、いい気分になってきました。緑の葉が茂る森の小道を歩いてズンズン行くと、小川があったり池があったり、小鳥が飛んでいたり、さえずっていたり。「ステキね。なんだか、森の動物たちにも出会えそうね。こんな気持ちが森気分って言うのかしら」と、幸ちゃんはつぶやきました。
幸ちゃんは、まだまだ描いています。お母さんが冷たく冷えたジュースを持ってきました。「まだ描いてるの?もういい加減にしたら?」。夢中になっている幸ちゃんに言いました。「本当に木が生えてきたら、どうするつもり?」と、お母さんが止めました。「まさか?大丈夫、大丈夫。でも、本当にそうなったらもっとステキね。」と、幸ちゃんは言いました。
ピンポーン。そのとき、玄関のチャイムが鳴りました。玄関にいたのは野ウサギと野ネズミの二匹です。「ごめんください」と、野ウサギが言いました。「ごめんください」と、野ネズミも続けました。「ええ?家を間違えていませんか?」と、ドアを開けたお母さんが応じました。「いえ。突然ですが、こちらに森があると聞きまして、寄らせていただきました。」と、野ウサギが丁寧に話しました。「僕たち、森がないと、暮らせないものですから」と、野ネズミもお願いしました。二匹はドンドン部屋の中に入ってきました。「ああ、ここだ、ここだ。この森で暮らしたいと思いまして」と、野ウサギが言いました。幸ちゃんは、あきれています。「だって、これは森の絵でしょう?しかも、本当は森の絵でなんかじゃあなくて、これがお母さんで、これがお菓子。でも、緑一色だから、森みたいになってしまったの」。「いえ。すばらしい森です」と、野ウサギは言いました。「では、失礼します」と、野ネズミが言ったかと思うと、二匹の姿は見えなくなり、どこかに消えてしまいました。
二匹は絵の森の中にいました。「やあ、やあ。いい森だ。ヒノキ、スギ、ケヤキ、クス、カシ・・・。近頃では、こんなに木が育った森はなかなか見つけられないよ」と、野ウサギが言いました。「まさに、『ランラン森気分』だね」と、野ネズミが応じました。「人間って、本当は森が好きなんだね」「そうさ。木も森も大好きさ。だけど、どうして、森を荒らしてしまったんだろう?」「どうして、森を荒らしてしまったんだろう?」二匹は、腕組みをして首をひねりました。「もう、本当の森なんて、どこにもないんだから」と、野ウサギが嘆きました。「もう、本当の森なんて、どこにもないよね」と、野ネズミが応じました。
幸ちゃんは、まだまだお絵描きを続けました。そのたびに、絵の森では新しい木がニョキと生えてきます。一本、また一本。クレヨンを変えると、木も変わります。「最高だね!」と、野ネズミが言いました。「幸ちゃん、もっと描いてね」と、野ネズミは精一杯大きな声を出しました。幸ちゃんには、何か小さな声で「森を守ってね」と、言っているのが聞こえたような気がしました。「木や自然を大切にね」と、言っているような気もしました。
ピンポーン。チャイムが鳴りました。玄関には、イノシシの親子とリスがいました。「まあ、今度はイノシシとリスなの?」と、お母さんがあきれて言いました。「失礼します」と言いながら、三匹はドンドン入ってきました。「この子が熱を出しているの。森にいるのが一番の治療だから、お願いします。こちらの森は最高だと聞きましたので・・・」と、お母さんイノシシが頼みました。「虫歯になってしまったんです。痛くて、痛くて、こんなに腫れているんです。こちらの森には、いい歯医者さんがいるって聞きましたので」と、リスも頼みました。「え?歯医者さん?」は、幸ちゃんは不思議そうな顔をしました。そのとき、絵の森の中から、さきほどの野ウサギが顔を出しました。「ああ、幸ちゃん、僕のことです。じゃあ、ちょっと見せてもらおうか?」と、言いながら、野ウサギとイノシシの親子とリスは、絵の森の中に消えていきました。
森の中では、お母さんイノシシが「風も涼しいし、木も茂って、ステキな森ね。これなら、うちの坊やもすぐに直りそう」と、ほっと一息つきました。リスは大きな口を開けて、野ウサギの治療を受けていますので話せませんでしたが、大きく一つうなずきました。「こんなにステキな森は、もうどこにもありませんね」と、お母さんイノシシは言いました。リスは痛みをこらえていますので話せませんでしたが、力強くうなずきました。
ピンポーン。「ほら、またお客さんよ」と、幸ちゃんは言いました。「今度は誰なの?」。「森林環境研究所の者です」と、自己紹介をしたのは、サルとクマでした。「もう、勝手にして」と、幸ちゃんは思いました。「こちらの森の二酸化炭素吸収率が極めて高いと聞いたものですから、調査に伺いました。地球温暖化対策を進める京都議定書で、我が国は二酸化炭素など温室効果ガスを1990年比で6%削減することを義務付けられているのです」と、舌をかみそうになりながらサルが言いました。「こちらの森の京都議定書達成に向けての積極的な取り組みが・・・」と、クマが言いかけたとき、「『こちらの森』とか、言うのやめていただけませんか?うちには本当の森なんてありませんし、この絵だって下手くそかも知れないけど、お母さんの顔やお菓子を描いたものなんです」と、幸ちゃんはさえぎりましたが、二匹は絵の森の中に消えてしまいました。
サルは奇妙な器械を取り出して、森の空気を測りました。「うーん。最高の環境だ。木は光合成をすることで二酸化炭素を吸収して炭素を取り込んで育ち、吸収量は木の重量に比例するんだ」と、研究所員らしく言いました。クマは大きく深呼吸をして、森の空気を味わいました。「うーん。『ランラン森気分』最高の味だ。ハチミツの匂いもするぞ」と、舌なめずりをしました。
「人間って、本当は森が好きなんだね」「そうさ。木も森も大好きさ。だけど、どうして、森を荒らしてしまったんだろう?」「どうして、森を荒らしてしまったんだろう?」。野ウサギも野ネズミもイノシシの親子もリスもサルもクマも、全員が腕を組んで首をひねりました。「そうだ」と、野ウサギが提案しました。「僕たちも、森の絵を描いてあげよう。幸ちゃんたちが森の暮らしを楽しめるようにさ」。野ウサギも野ネズミもイノシシの親子もリスもサルもクマも、全員で森の絵を描きました。緑、緑、緑一色のクレヨンでヒノキやスギやケヤキやカエデやクス・・・、木や葉っぱやクルクルやグチャグチャやヘンテコリンやメチャクチャや、それでも、なぜか森に見える絵を描きました。絵の森では、木がもっともっとたくさん生えてきました。
「さあ、幸ちゃんを迎えにいこう」。野ウサギが幸ちゃんを迎えにいきました。「幸ちゃん、僕たちの森に遊びに来ない?」と、野ウサギが誘いました。幸ちゃんは少し考えて「うん、連れて行ってもらうわ」と、答えました。「じゃあ、ちょっとだけ目をつぶって」。
遠くで叫ぶ幸ちゃんの声が、絵の森の中から聞こえてきました。「ねえ。お母さん。本当の木が生えているよ。何本も何本も生えているよ」と、言っているように聞こえました。「やったー!これで、幸ちゃんも森の恵みを味わえるね」「よかったね」と、絵の森の中では、野ウサギも野ネズミもイノシシの親子もリスもサルもクマも、みんな大喜びでした。イノシシの坊やもすっかり元気になっていました。虫歯のリスも、もうニコニコ顔です。木々の葉は風にそよぎ、いつの間にか小鳥たちも舞っています。幸ちゃんは、思いっきり深呼吸して、森の空気をいっぱい吸い込みました。森林環境研究所員のサルが「我が国の森林の約40%を占める人工林は、外材の輸入増加等による林業の不振で、間伐などの手入れが行われにくくなっています。このままでは水を貯める力も土砂崩れを防ぐ力も失われてしまします」と、生意気そうに力説しました。「まあまあ、それも大切な話かもしれないけど、幸ちゃん、『ランラン森気分』だね」と、クマが言いました。「そうそう、それも大事な話かもしれないけど、『ランラン森気分』だわ」と、幸ちゃんも応えました。「ところで、あのクレヨンって、何だったのかしら?」と、幸ちゃんが尋ねました。「ああ、あれは僕の発明です」と、野ネズミが答えました。「あの、下手くそな絵は?」「あれはイノシシの坊やの絵です。僕は森の発明家だし、イノシシ坊やは画家の卵です。ステキでしょう?」と、野ネズミは続けました。「ときどき遊びに来てもいいかしら?」「もちろん。大歓迎さ」と、みんな声をそろえて言いました。幸ちゃんは、「森の緑もステキ。森の仲間もステキ。森って最高!」と、両手を突き上げて叫びました。
お母さんもニコニコしながら、大きな声で呼びました。「幸ちゃーん、夕ご飯の時間ですよー。帰ってらっしゃーい!」。「ハーイ」。絵の森の中からは「ランランラン♪森きぶ~ん♪」の大合唱が聞こえてきました。
2021年08月02日
森の香りをお届けします
「野菜はいかがですか?」と、リヤカーを引いたおじいさんを見かけるようになったのは、数日前から。おじいさんのリヤカーには、ナスやトマト、キュウリにエダマメ、トウモロコシに大きなスイカなどがどっさり積まれています。「新鮮な野菜をお届けしまーす」。不慣れなためか、小さな声です。それに、いくら近くの森といっても、リヤカーを引いて来るのであれば、3時間はたっているはず。にもかかわらず、野菜たちはどれもこれも、朝露が残るほどに新鮮となれば、かえって疑われ、「あれは、きっと水をかけているんだわ」「朝採ってきたって、嘘に決まっているわよね」と、これは口うるさい団地のお母さんたちの噂です。
リヤカーには、野菜のほかに、白い紙袋がいくつも積んでありました。風船みたいに丸く膨らんでいましたが、手で持ってみても振ってみても音がするわけでなく中で何か動くわけでなく、ただ軽いだけで、おじいさんに言わせれば「森の風が詰まっているんだよ」とのことでしたが、「それは、嘘よね」「あれは、空っぽよ」というのが、お母さんたちの一致した結論でした。ですから、おじいさんのリヤカーは毎回、野菜を売り残して帰っていきます。もちろん、白い紙袋もどっさり残ったまま。
幸ちゃんは、「かわいそう」と思いました。でも、お母さんに聞いた話だと、紙袋の中には、何も入っていないとのことでしたが、幸ちゃんには「あんなに膨らんでいるんだから、きっと何かいいものが詰まっているんだわ」と、考えていました。嘘つきと言われたおじいさんの野菜は、全然売れません。夏休みに入ったばかりのその日も、麦わらぼうしをウチワにして大きなため息を一つ。肩を落として帰っていこうとしていました。
「きっと、いいものが詰まっているはず」幸ちゃんは、思い切って後をついて行くことに決めました。街角をいくつも曲がり、信号を過ぎスーパーの前を通り、途中何度も汗を拭いて腰を伸ばして、やっと畑の見えるところで一休み。幸ちゃんも少し離れた道端で立ち止まりました。すると、おじいさんは紙袋を一つ取り上げ、ポンと両手ではさんで割りました。おじいさんが深呼吸したすぐ後、幸ちゃんのところに爽やかな涼しい風が吹き抜けました。「あれ?どうしたんだろう?」と、幸ちゃんは少し不思議に思いました。その風には、いい香りが混ざっていたのです。
「ああ、いい匂い。葉っぱや草の匂いだわ」と、幸ちゃんは思いました。「これって、あの紙袋の中から?」幸ちゃんは、少し疑ってみました。その時おじいさんが、もう一つ紙袋を割りました。ポン。気持ちのいい音が響き、またまた涼しい風が吹きすぎました。「やっぱり、間違いなし。お母さんは、嘘つきとか言っていたけど、嘘つきじゃなくて、あのおじいさんはきっと魔法使いのおじいさんだわ」と、ほっぺたをつねってみました。
幸ちゃんは、いつの間にかリヤカーに近づき、「ねえ、おじいさん。その袋には何が入ってるの?」と、聞いてみました。ちょっとびっくりしたようなおじいさんは、幸ちゃんに紙袋を一つ渡して「割ってごらん」と言いました。ポン。幸ちゃんが袋を乗せた両手を合わせると、紙風船が割れるように袋は割れて、小鳥のさえずりを乗せた風が、さーっと吹き抜けました。よく見ると、リヤカーに積まれた野菜たちは、朝露のような水滴に包まれています。水滴の一粒一粒が真夏の太陽の光を受けて、キラキラと虹色に輝いています。
「君の名前はなんていうの?」と、おじいさが聞きました。「私は幸子よ。おじいさんは?」「幸ちゃんか?ワシは源助」「源助おじいさんか?」「まあ、そんなところだな」と、おじいさんは照れくさそうに笑いました。「この紙袋に森の風を詰めているのは、うちのばあさんでね。ワシらが吸っている森の空気を、街の人たちにも届けてあげたいと言い出してね。毎日紙で袋を作って、森の風を詰めているんだよ」。「おばあさんは元気なの?」「元気だよ。うちで待っているばあさんに、甘いお菓子でも買って帰ってあげたいけど、野菜が売れないからね」。「森の風は冷たいだけじゃあなくて、雲を作り、雨を降らせ、木を育て、森を育て、野菜も育て、何でも叶う魔法の風なんだよ」。「そんな風を、幸ちゃんたちにも届けてあげたいんだけど、誰も話を聞いてくれないんだ」と、おじいさんは嘆きました。「私でも役に立つことはないかしら?」と、幸ちゃんは聞いてみました。「私、手伝ってあげる。源助おじいさん、もう一度、街に戻ろう!」と、言いながらリヤカーの後ろを押しながら、無理やり向きを変えてしまいました。「おい、おい。幸ちゃん」と、困り顔のおじいさんは渋々街に引き返すことにしました。
「森の香りをお届けしまーす」と、今度は幸ちゃんが大声で叫びました。「森の香りをお届けしまーす」と、おじいさんも少し大きな声で呼びました。団地の広場には、あっという間にお母さんたちや、子供たちがあふれました。「ああ、あの嘘つきのおじいさんだわ」「女の子の声だったので、だまされちゃった」と、口々に言いながら帰ろうとしています。「さあ、源助おじいさん。紙袋を割って」と、幸ちゃんが言いました。ポンと音を立てて、袋が一つ割れました。辺りは、森の香りに包まれ、涼しい風が吹きぬけ、野菜たちはみずみずしい水滴をつけました。帰ろうとしていたお母さんたちの足が止まりました。子供たちも驚いた表情で戻ってきました。
「何の匂い?」「何かしたんでしょう?」と、幸ちゃんとおじいさんは問い詰められました。「違います。紙袋に詰めた森の風が広がっただけです。源助じいさんとおばあさんが、心を込めて詰めた森の風です。」と、幸ちゃんは叫びました。「そんなわけないじゃない」と、お母さんの一人が紙袋を割りました。「あっ」。さっきと同じです。「私もやってみていいかしら?」と、別のお母さんも割ってみました。「あーいい匂い。森の香りだわ」。「私も」「僕も」と、紙袋は次々と割られました。森の香りが立ち上りました。炎天下とは思えないほどに涼しくなり、広場に植えられた木々も草花も、元気を取り戻し、そこだけ空気も澄んで、二人にはみんなの笑顔がはっきりと見えました。
「なんて新鮮なナスなの」と、一人のお母さんがリヤカーの中のナスを手に取りました。「キュウリだって新鮮よ」と、別のお母さんはキュウリを買いました。「私はスイカをいただくわ」「トウモロコシをちょうだい」と、野菜たちは飛ぶように売れていきます。「ありがとうございます。森の風はプレゼントです」と、おじいさんは大喜びです。「ありがとうございます」と、幸ちゃんも紙袋を配ります。幸ちゃんの友達もお手伝いです。幸ちゃんのお母さんも真っ赤なトマトを一袋買ってくれました。
「売り切れだね。幸ちゃん、ありがとう。ばあさんには、アイスクリームでも買って帰るよ」と、おじいさんは、うれしそうにお礼を言いました。「アイスクリームなんてダメよ。だって融けちゃうもん」と、幸ちゃんは言いました。「大丈夫。紙袋の中に入れていくから」「うん。それなら大丈夫だね。源助おじいさん、また来てね。それから、いつか私、おばあさんを手伝って、森の風を紙袋に詰めてみたいな」。「はい、お礼は森の風でいいかな?」二人は、約束をして別れました。
次の日、幸ちゃんは朝から紙袋を作って待っていました。何枚も何枚も作りました。「森の香りをお届けしまーす」と、おじいさんの声が聞こえました。幸ちゃんは、外に飛び出しました。あちらからもこちらからも、お母さんや子供たちがニコニコしながら出てきました。おじいさんのリヤカーには、大きな大きな紙袋とおばあさんも乗っていました。「幸ちゃん、昨日はありがとう。ばあさんが、どうしてもお礼を言いたいといったからね」と、おじいさんは話しました。「幸ちゃん、昨日はありがとう。おじいさんから話を聞いて、どうしても会ってみたかったから、無理を言って乗せてきてもらったんだよ」と、おばあさんは、顔をくしゃくしゃにして言いました。「想像していた通りに可愛い子だね。これは、お礼の森の風だよ。今朝、ようやく太陽が昇る頃に森に吹いていた特別な風だよ。幸ちゃんにあげようと、いっぱい詰めてきたからね」。
「わーうれしい。これ全部、私のもの?私もね、紙袋をこんなに作ったの。でも、こんなに大きくはないわ」と、大喜び。「幸子、ここで袋を開けたら?」と、幸ちゃんのお母さんが言いました。「そうね。さあ、開けるわよ」と、幸ちゃんは叫びました。「みんな、いいー?イチ、二のサン」。
風が吹きました。もくもくと雲も湧きました。雲は高く高く上っていき、気持ちのいい雨が降り始めました。雨上がりには太陽が顔を出し、美しい七色の虹も架かりました。歓声が上がって、森の香りが立ち込めました。「森の風って、すごいね」「森の香りって、命の香りだね」。みんな口々に叫びました。しおれかけていた木々がピンと背筋を伸ばしました。小鳥がさえずりました。虫やカエルたちも命の歌を合唱し始めました。「源助おじいさん、ありがとう」と、幸ちゃんはおじいさんに飛びつきました。
「幸子、何してるの?」お母さんの声で、目が覚めました。幸ちゃんは、公園のケヤキの木にしがみついている自分に気がつきました。「あれ?源助おじいさんは?」「何言ってるの?昼寝していたかと思ったら、突然ケヤキの木にしがみついて」と、お母さん。「え?今のは全部夢だったの?」。「風は?雨は?虹は?」。
その時「野菜はいかがですか?新鮮な野菜をお届けしまーす」と呼ぶ声が聞こえてきました。「ほら、やっぱり源助おじいさんだ」と、幸ちゃんは走り出しました。でも、止まっていたのは拡声器のついた軽トラック。よく聞くと、その声は源助おじいさんとはまったく別の人の声でした。「ねえ、お母さん、トマトを買ってね。真っ赤なトマトを売っていると思うから。できれば、朝露がいっぱいついたのをお願い」と、幸ちゃんは、少しがっかりしたような小さな声でつぶやきました。
「それから、もしかして、もしかして白い紙袋があったら、忘れずに一つもらってね。私ね、私ね、森の香りが大好きだから」。
リヤカーには、野菜のほかに、白い紙袋がいくつも積んでありました。風船みたいに丸く膨らんでいましたが、手で持ってみても振ってみても音がするわけでなく中で何か動くわけでなく、ただ軽いだけで、おじいさんに言わせれば「森の風が詰まっているんだよ」とのことでしたが、「それは、嘘よね」「あれは、空っぽよ」というのが、お母さんたちの一致した結論でした。ですから、おじいさんのリヤカーは毎回、野菜を売り残して帰っていきます。もちろん、白い紙袋もどっさり残ったまま。
幸ちゃんは、「かわいそう」と思いました。でも、お母さんに聞いた話だと、紙袋の中には、何も入っていないとのことでしたが、幸ちゃんには「あんなに膨らんでいるんだから、きっと何かいいものが詰まっているんだわ」と、考えていました。嘘つきと言われたおじいさんの野菜は、全然売れません。夏休みに入ったばかりのその日も、麦わらぼうしをウチワにして大きなため息を一つ。肩を落として帰っていこうとしていました。
「きっと、いいものが詰まっているはず」幸ちゃんは、思い切って後をついて行くことに決めました。街角をいくつも曲がり、信号を過ぎスーパーの前を通り、途中何度も汗を拭いて腰を伸ばして、やっと畑の見えるところで一休み。幸ちゃんも少し離れた道端で立ち止まりました。すると、おじいさんは紙袋を一つ取り上げ、ポンと両手ではさんで割りました。おじいさんが深呼吸したすぐ後、幸ちゃんのところに爽やかな涼しい風が吹き抜けました。「あれ?どうしたんだろう?」と、幸ちゃんは少し不思議に思いました。その風には、いい香りが混ざっていたのです。
「ああ、いい匂い。葉っぱや草の匂いだわ」と、幸ちゃんは思いました。「これって、あの紙袋の中から?」幸ちゃんは、少し疑ってみました。その時おじいさんが、もう一つ紙袋を割りました。ポン。気持ちのいい音が響き、またまた涼しい風が吹きすぎました。「やっぱり、間違いなし。お母さんは、嘘つきとか言っていたけど、嘘つきじゃなくて、あのおじいさんはきっと魔法使いのおじいさんだわ」と、ほっぺたをつねってみました。
幸ちゃんは、いつの間にかリヤカーに近づき、「ねえ、おじいさん。その袋には何が入ってるの?」と、聞いてみました。ちょっとびっくりしたようなおじいさんは、幸ちゃんに紙袋を一つ渡して「割ってごらん」と言いました。ポン。幸ちゃんが袋を乗せた両手を合わせると、紙風船が割れるように袋は割れて、小鳥のさえずりを乗せた風が、さーっと吹き抜けました。よく見ると、リヤカーに積まれた野菜たちは、朝露のような水滴に包まれています。水滴の一粒一粒が真夏の太陽の光を受けて、キラキラと虹色に輝いています。
「君の名前はなんていうの?」と、おじいさが聞きました。「私は幸子よ。おじいさんは?」「幸ちゃんか?ワシは源助」「源助おじいさんか?」「まあ、そんなところだな」と、おじいさんは照れくさそうに笑いました。「この紙袋に森の風を詰めているのは、うちのばあさんでね。ワシらが吸っている森の空気を、街の人たちにも届けてあげたいと言い出してね。毎日紙で袋を作って、森の風を詰めているんだよ」。「おばあさんは元気なの?」「元気だよ。うちで待っているばあさんに、甘いお菓子でも買って帰ってあげたいけど、野菜が売れないからね」。「森の風は冷たいだけじゃあなくて、雲を作り、雨を降らせ、木を育て、森を育て、野菜も育て、何でも叶う魔法の風なんだよ」。「そんな風を、幸ちゃんたちにも届けてあげたいんだけど、誰も話を聞いてくれないんだ」と、おじいさんは嘆きました。「私でも役に立つことはないかしら?」と、幸ちゃんは聞いてみました。「私、手伝ってあげる。源助おじいさん、もう一度、街に戻ろう!」と、言いながらリヤカーの後ろを押しながら、無理やり向きを変えてしまいました。「おい、おい。幸ちゃん」と、困り顔のおじいさんは渋々街に引き返すことにしました。
「森の香りをお届けしまーす」と、今度は幸ちゃんが大声で叫びました。「森の香りをお届けしまーす」と、おじいさんも少し大きな声で呼びました。団地の広場には、あっという間にお母さんたちや、子供たちがあふれました。「ああ、あの嘘つきのおじいさんだわ」「女の子の声だったので、だまされちゃった」と、口々に言いながら帰ろうとしています。「さあ、源助おじいさん。紙袋を割って」と、幸ちゃんが言いました。ポンと音を立てて、袋が一つ割れました。辺りは、森の香りに包まれ、涼しい風が吹きぬけ、野菜たちはみずみずしい水滴をつけました。帰ろうとしていたお母さんたちの足が止まりました。子供たちも驚いた表情で戻ってきました。
「何の匂い?」「何かしたんでしょう?」と、幸ちゃんとおじいさんは問い詰められました。「違います。紙袋に詰めた森の風が広がっただけです。源助じいさんとおばあさんが、心を込めて詰めた森の風です。」と、幸ちゃんは叫びました。「そんなわけないじゃない」と、お母さんの一人が紙袋を割りました。「あっ」。さっきと同じです。「私もやってみていいかしら?」と、別のお母さんも割ってみました。「あーいい匂い。森の香りだわ」。「私も」「僕も」と、紙袋は次々と割られました。森の香りが立ち上りました。炎天下とは思えないほどに涼しくなり、広場に植えられた木々も草花も、元気を取り戻し、そこだけ空気も澄んで、二人にはみんなの笑顔がはっきりと見えました。
「なんて新鮮なナスなの」と、一人のお母さんがリヤカーの中のナスを手に取りました。「キュウリだって新鮮よ」と、別のお母さんはキュウリを買いました。「私はスイカをいただくわ」「トウモロコシをちょうだい」と、野菜たちは飛ぶように売れていきます。「ありがとうございます。森の風はプレゼントです」と、おじいさんは大喜びです。「ありがとうございます」と、幸ちゃんも紙袋を配ります。幸ちゃんの友達もお手伝いです。幸ちゃんのお母さんも真っ赤なトマトを一袋買ってくれました。
「売り切れだね。幸ちゃん、ありがとう。ばあさんには、アイスクリームでも買って帰るよ」と、おじいさんは、うれしそうにお礼を言いました。「アイスクリームなんてダメよ。だって融けちゃうもん」と、幸ちゃんは言いました。「大丈夫。紙袋の中に入れていくから」「うん。それなら大丈夫だね。源助おじいさん、また来てね。それから、いつか私、おばあさんを手伝って、森の風を紙袋に詰めてみたいな」。「はい、お礼は森の風でいいかな?」二人は、約束をして別れました。
次の日、幸ちゃんは朝から紙袋を作って待っていました。何枚も何枚も作りました。「森の香りをお届けしまーす」と、おじいさんの声が聞こえました。幸ちゃんは、外に飛び出しました。あちらからもこちらからも、お母さんや子供たちがニコニコしながら出てきました。おじいさんのリヤカーには、大きな大きな紙袋とおばあさんも乗っていました。「幸ちゃん、昨日はありがとう。ばあさんが、どうしてもお礼を言いたいといったからね」と、おじいさんは話しました。「幸ちゃん、昨日はありがとう。おじいさんから話を聞いて、どうしても会ってみたかったから、無理を言って乗せてきてもらったんだよ」と、おばあさんは、顔をくしゃくしゃにして言いました。「想像していた通りに可愛い子だね。これは、お礼の森の風だよ。今朝、ようやく太陽が昇る頃に森に吹いていた特別な風だよ。幸ちゃんにあげようと、いっぱい詰めてきたからね」。
「わーうれしい。これ全部、私のもの?私もね、紙袋をこんなに作ったの。でも、こんなに大きくはないわ」と、大喜び。「幸子、ここで袋を開けたら?」と、幸ちゃんのお母さんが言いました。「そうね。さあ、開けるわよ」と、幸ちゃんは叫びました。「みんな、いいー?イチ、二のサン」。
風が吹きました。もくもくと雲も湧きました。雲は高く高く上っていき、気持ちのいい雨が降り始めました。雨上がりには太陽が顔を出し、美しい七色の虹も架かりました。歓声が上がって、森の香りが立ち込めました。「森の風って、すごいね」「森の香りって、命の香りだね」。みんな口々に叫びました。しおれかけていた木々がピンと背筋を伸ばしました。小鳥がさえずりました。虫やカエルたちも命の歌を合唱し始めました。「源助おじいさん、ありがとう」と、幸ちゃんはおじいさんに飛びつきました。
「幸子、何してるの?」お母さんの声で、目が覚めました。幸ちゃんは、公園のケヤキの木にしがみついている自分に気がつきました。「あれ?源助おじいさんは?」「何言ってるの?昼寝していたかと思ったら、突然ケヤキの木にしがみついて」と、お母さん。「え?今のは全部夢だったの?」。「風は?雨は?虹は?」。
その時「野菜はいかがですか?新鮮な野菜をお届けしまーす」と呼ぶ声が聞こえてきました。「ほら、やっぱり源助おじいさんだ」と、幸ちゃんは走り出しました。でも、止まっていたのは拡声器のついた軽トラック。よく聞くと、その声は源助おじいさんとはまったく別の人の声でした。「ねえ、お母さん、トマトを買ってね。真っ赤なトマトを売っていると思うから。できれば、朝露がいっぱいついたのをお願い」と、幸ちゃんは、少しがっかりしたような小さな声でつぶやきました。
「それから、もしかして、もしかして白い紙袋があったら、忘れずに一つもらってね。私ね、私ね、森の香りが大好きだから」。
2021年08月01日
ねえ?森の話を聞かせて
森の小さな学校からの帰り道は、緑の匂いがいっぱい。木の葉を透かした陽の光が、ユラリユラリ、キラリキラリと輝いています。子供たちがみんな帰った放課後、ランドセルを背負った健ちゃんがたった一人で森の小道を歩いていたときのことです。風の音に混じって、何処からか、ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリンと美しい歌声が聞こえてきました。健ちゃんは思わず立ち止まってしまいました。
「あれっ?何の声?」今年の春、病気で入院したお母さんから離れ、森のおばあちゃんの家に引越してきたばかりの健ちゃんでも、スズメやツバメが美しい声でさえずること、コオロギやスズムシがリーンリーンと涼しげに鳴くことは知っていましたが、その歌声は今まで聞いたことのない、もっともっときれいで、澄んだ森の水が流れ出るような美しい声でした。「あれっ?何が鳴いているのかな?」キョロキョロと辺りを見回してみました。
健ちゃんには、何が鳴いているのか分かりません。何処から聞こえてくるのかさえ分かりませんでした。空から降ってくるようでもあり、地面の下から湧いてくるようでもあり。「どうやら、こっちの方から聞こえてくるぞ」そこに立っていたのは、一本のクスノキでした。濃い緑の葉っぱをいっぱい付けて、何十年も何百年もここに立ち続け、太い根っこで世界をがっちりとつかんでいるような神様みたいな木でした。「あっ。この中からだ」。木の幹に耳を当ててみました。「やっぱり、この中だ。フクロウの赤ちゃんでもいるのかな?」健ちゃんは大きな木の胴にぽっかりと開いた穴の中を覗き込んでみました。「おーい。誰かいるのかい?」
ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリンという歌声はますます大きく聞こえてきます。じーっと耳を澄まして聞いていると、まるでピアノの音のようでもあり、オルゴールの音のようでもあり。「健ちゃん、健ちゃん」と友だちみたいに呼んでいるようでもあり、「私の話を聞いていかないか?」と誘っているようでもあり。「森の精かな?」以前、お母さんが読んでくれた本に出てきた、小人みたいな森の精のことを思い出しました。
健ちゃんが覗き込んだ暗い穴の中には、フクロウでも森の精でもなく、ホタルみたいにピカピカと光った真っ黒なカブトムシが一匹いました。「えーっ?カブトムシ?」健ちゃんは、カブトムシに向かって「今鳴いていたのは、君かい?」と聞いてみました。カブトムシは自慢の角を振り振り答えました。「もちろん僕だよ。森の歌を聞いていってね」ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリン。
「ただいまー」健ちゃんはランドセルを放り出すと、家の裏山の道を駆け出しました。手にはカブトムシをつまんで、ドンドンドンドン駆け上がりました。やっと空が大きく見える頂上まで来ました。健ちゃんは、遠くにこの春まで暮らしていた街が見えるこの裏山が大好きです。「ねえ、カブトムシ君。さっきみたいに、歌ってよ」カブトムシは歌いませんでしたが、「ヒューっ」と深呼吸。「あのね・・・」と、角を振り振り話し始めました。入院中の健ちゃんのお母さんが、健ちゃんと会えるのを楽しみに待っていること、さっき健ちゃんのおばあちゃんが、お母さんに届けようと、健ちゃんの描いたお母さんの絵を大事そうに丸めて足早に病院に向かったことなどを話してくれました。「僕たちは、もう友だちだね」と健ちゃん。「そうだよ。友だちさ」と、カブトムシは答えました。
翌日、健ちゃんは、カブトムシを学校に連れて行き、学校のみんなの前で鳴かせてみせることにしました。
みんなが集まって席につきました。「さあ、音楽会の始まりでーす」健ちゃんは得意満面。でも、カブトムシは角は振っても、鳴いてはくれません。「ねえ、鳴いてよーっ!」
「嘘つき。健ちゃんの嘘つき。カブトムシが鳴くわけないよ」
健ちゃんは、すっかり落ち込んでしまいました。「嘘じゃあないもん。確かに鳴いたんだもん」
「カブトムシ君。みんなの前では、どうして鳴いてくれなかったの?」「ごめん、ごめん。実は鳴いていたのは僕じゃあなかったんだ」「森にはおしゃべり好きは大勢いるけど、誰でも歌えるわけじゃあないんだ」と謝りました。
数日後の帰り道、またあの木のそばを通りかかったとき、この間と同じようにピロピロピピピ・ピンコロピンコロリンという歌声が聞こえてきました。
歌声はますますはっきりと聞こえてきます。「うん。確かに聞こえる」。「ねえ、森の歌を聞いていってね」覗いた穴の中にはコオロギでもスズムシでもなく、偉そうにタクトのように前足を振りかざし、緑の燕尾服を身にまとったカマキリがいました。「えーっ?カマキリ?」健ちゃんはカマキリに向かって「今のは君の歌声かい?」と聞いてみました。カマキリは、待ってましたとばかりに胸を張り「もちろん森の音楽家、私の歌ですよ」と答えました。
その日の晩、健ちゃんは布団に入って、お母さんのことを思い出していました。枕元のカマキリは鳴きませんでしたが、「ヒューっ」と深呼吸。「あのね・・・」と音楽家らしくタクトを振りかざして話し始めました。健ちゃんのお父さんが、今度の日曜日には森の家に来ること、そのとき、少し良くなったお母さんも一緒に来るかも知れないことなどを話してくれました。「えーっ、本当?僕たちは、もう友だちだね」「もちろん。ずっと前から友だちさ」と、カマキリは答えました。健ちゃんは嬉しくて嬉しくて、なかなか眠られませんでした。
翌日、健ちゃんは、カマキリを連れて学校に行きました。みんなが席につきました。「さあ、音楽会の始まりでーす」健ちゃんは今度こそと自信満々。でも、カマキリはタクトは振っても鳴いてはくれません。「ねえ、鳴いてよーっ!」
「嘘つき!健ちゃんの嘘つき。カマキリが鳴くわけないよ」「嘘つき、嘘つき!」「カブトムシだって鳴かないし、カマキリだって鳴くわけないよ」。みんな大騒ぎです。もう取り返しがつきません。
そのとき、幸子先生がニコニコと笑いながら「私は、健ちゃんが嘘つきだとは思いません。健ちゃんが聞いたという歌声を、みんなで聞きに行ってみましょう」と、助け舟を出してくれました。健ちゃんが先頭に立って、あのクスノキの根元まで来ました。すると、何処からともなく、あのピロピロピピピ・ピンコロピンコロリンというきれいな歌声が確かに聞こえてきました。「ほらねっ、嘘つきなんかじゃないよね」
「本当だ。聞こえる、聞こえる」みんな大喜びです。「でも、何の声だろう?」誰も答えることはできませんでした。カマキリは言いました。「ごめんなさい。鳴いたのは、私じゃあありません」。カブトムシも謝りました。「僕でもありませんでした」。
みんな代わる代わる木の幹に耳を押し付けて聞いています。「みなさん、これはね。このクスノキが森の話をしている声ですよ」と幸子先生が教えてくれました。「私も子供の頃、よく聞きに来ました」とニッコリ。「そうなんだ!この神様の木が歌っていたんだ」健ちゃんも、謎が解けてニッコリと笑いました。学校のみんなも、カブトムシもカマキリも顔を見合わせてニッコリと笑いました。
クスノキは生まれ育った頃の森で見たこと、聞いたことを話してくれました。森の虫や動物や子供たちと仲良く遊んだこと。リスもムササビもクスノキの枝で遊んだこと。小鳥たちがたくさんのかわいいかわいいヒナを育てたこと。親鳥の心配をよそに、次から次へと弱々しい羽ばたきで、大空へと巣立っていったこと。
幾時代かが過ぎて、いつの間にか人間の子供たちの笑い声が聞こえなくなったこと、外国の飛行機がいくつもいくつも落とした火の玉のこと、街が真っ赤に燃えたこと、何人もの人が泣きながら死んでいったこと。
やがて、鉄の機械がやってきて、トンネルやダムや車の走る道路ができたこと。そのために木々は切り倒され、谷に捨てられたこと。人間が植えた杉やヒノキが、息苦しさからか、悪い病気に罹ったこと。大風が吹き荒れ、洪水が起こり、森の形がすっかり変わってしまったこと。
それでも、再び子供たちが明るい声で歌い始めて、ほっとしたこと。心の優しい幸子先生や健ちゃんと出会い友だちになったこと。大きく息を吐きながら、ゆっくりゆっくりと聞かせてくれました。ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリン。その度に、辺りには涼やかに澄んだ空気が広がり、子供たちも幸子先生も、深く深く息を吸い込みました。
「健ちゃんって、すごい」「このクスノキと友だちなんだ」みんな声をそろえて叫びました。「ねえ?森の話を聞かせて」「もっともっと、森の話を聞かせて」。歌声はますます大きく、夕日に赤々と輝く山々に響きわたりました。
健ちゃんは、神様みたいなクスノキと友だちになったんです。もちろん学校のみんなとも仲のいい友だちです。カブトムシもカマキリも、森のみんなが友だちです。
「お母さん、僕、みんなと友だちになったよ。もう、寂しくなんかないよ」その晩、健ちゃんはお母さんに手紙を書きました。「お母さん、森には大きなクスノキが立っているんだよ。何でも見ていて、何でも知っていて、何でも話してくれる神様の木だから、お母さんの病気もきっと治してくれるよ。お母さん、早く良くなってね。僕、森が大好きだよ」
やがて新しい季節を迎えた頃、健ちゃんは、元気になって迎えに来たお母さんと、街に戻ることになりました。森のみんなが見送ってくれました。お母さんと一緒に神様の木にも「ありがとう」と「サヨナラ」を言いに行きました。クスノキは、ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリンといつものきれいな歌声を聞かせて見送ってくれました。「へーっ?お母さんも友だちだったんだ」「そうよ。私も子供の頃、このクスノキの話を何度も聞かせてもらったわ」と、お母さんも目に涙を浮かべながら、懐かしそうに聞いていました。「健ちゃんが生まれてきてくれた時にも、このクスノキに報告しに来たの。この木は何でも知っているのよ」。ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリン。
「ねえ?健ちゃん。森の話を聞かせて!」と、健ちゃんの友だちがやってきました。街に戻った健ちゃんは、半年暮らした森の話、神様の木から教えてもらった森の話を、クスノキにしてもらったのと同じようにゆっくりゆっくりと話しました。
街角のケヤキの木、学校や公園に立つドングリの木、秋に葉っぱの色を変える神社のイチョウの木、花や草や小さな鳥や虫たち。健ちゃんには、耳を澄ませば、どこにいても森の話が聞こえてきます。ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリン。健ちゃんは、ますます森が好きになりました。
「あれっ?何の声?」今年の春、病気で入院したお母さんから離れ、森のおばあちゃんの家に引越してきたばかりの健ちゃんでも、スズメやツバメが美しい声でさえずること、コオロギやスズムシがリーンリーンと涼しげに鳴くことは知っていましたが、その歌声は今まで聞いたことのない、もっともっときれいで、澄んだ森の水が流れ出るような美しい声でした。「あれっ?何が鳴いているのかな?」キョロキョロと辺りを見回してみました。
健ちゃんには、何が鳴いているのか分かりません。何処から聞こえてくるのかさえ分かりませんでした。空から降ってくるようでもあり、地面の下から湧いてくるようでもあり。「どうやら、こっちの方から聞こえてくるぞ」そこに立っていたのは、一本のクスノキでした。濃い緑の葉っぱをいっぱい付けて、何十年も何百年もここに立ち続け、太い根っこで世界をがっちりとつかんでいるような神様みたいな木でした。「あっ。この中からだ」。木の幹に耳を当ててみました。「やっぱり、この中だ。フクロウの赤ちゃんでもいるのかな?」健ちゃんは大きな木の胴にぽっかりと開いた穴の中を覗き込んでみました。「おーい。誰かいるのかい?」
ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリンという歌声はますます大きく聞こえてきます。じーっと耳を澄まして聞いていると、まるでピアノの音のようでもあり、オルゴールの音のようでもあり。「健ちゃん、健ちゃん」と友だちみたいに呼んでいるようでもあり、「私の話を聞いていかないか?」と誘っているようでもあり。「森の精かな?」以前、お母さんが読んでくれた本に出てきた、小人みたいな森の精のことを思い出しました。
健ちゃんが覗き込んだ暗い穴の中には、フクロウでも森の精でもなく、ホタルみたいにピカピカと光った真っ黒なカブトムシが一匹いました。「えーっ?カブトムシ?」健ちゃんは、カブトムシに向かって「今鳴いていたのは、君かい?」と聞いてみました。カブトムシは自慢の角を振り振り答えました。「もちろん僕だよ。森の歌を聞いていってね」ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリン。
「ただいまー」健ちゃんはランドセルを放り出すと、家の裏山の道を駆け出しました。手にはカブトムシをつまんで、ドンドンドンドン駆け上がりました。やっと空が大きく見える頂上まで来ました。健ちゃんは、遠くにこの春まで暮らしていた街が見えるこの裏山が大好きです。「ねえ、カブトムシ君。さっきみたいに、歌ってよ」カブトムシは歌いませんでしたが、「ヒューっ」と深呼吸。「あのね・・・」と、角を振り振り話し始めました。入院中の健ちゃんのお母さんが、健ちゃんと会えるのを楽しみに待っていること、さっき健ちゃんのおばあちゃんが、お母さんに届けようと、健ちゃんの描いたお母さんの絵を大事そうに丸めて足早に病院に向かったことなどを話してくれました。「僕たちは、もう友だちだね」と健ちゃん。「そうだよ。友だちさ」と、カブトムシは答えました。
翌日、健ちゃんは、カブトムシを学校に連れて行き、学校のみんなの前で鳴かせてみせることにしました。
みんなが集まって席につきました。「さあ、音楽会の始まりでーす」健ちゃんは得意満面。でも、カブトムシは角は振っても、鳴いてはくれません。「ねえ、鳴いてよーっ!」
「嘘つき。健ちゃんの嘘つき。カブトムシが鳴くわけないよ」
健ちゃんは、すっかり落ち込んでしまいました。「嘘じゃあないもん。確かに鳴いたんだもん」
「カブトムシ君。みんなの前では、どうして鳴いてくれなかったの?」「ごめん、ごめん。実は鳴いていたのは僕じゃあなかったんだ」「森にはおしゃべり好きは大勢いるけど、誰でも歌えるわけじゃあないんだ」と謝りました。
数日後の帰り道、またあの木のそばを通りかかったとき、この間と同じようにピロピロピピピ・ピンコロピンコロリンという歌声が聞こえてきました。
歌声はますますはっきりと聞こえてきます。「うん。確かに聞こえる」。「ねえ、森の歌を聞いていってね」覗いた穴の中にはコオロギでもスズムシでもなく、偉そうにタクトのように前足を振りかざし、緑の燕尾服を身にまとったカマキリがいました。「えーっ?カマキリ?」健ちゃんはカマキリに向かって「今のは君の歌声かい?」と聞いてみました。カマキリは、待ってましたとばかりに胸を張り「もちろん森の音楽家、私の歌ですよ」と答えました。
その日の晩、健ちゃんは布団に入って、お母さんのことを思い出していました。枕元のカマキリは鳴きませんでしたが、「ヒューっ」と深呼吸。「あのね・・・」と音楽家らしくタクトを振りかざして話し始めました。健ちゃんのお父さんが、今度の日曜日には森の家に来ること、そのとき、少し良くなったお母さんも一緒に来るかも知れないことなどを話してくれました。「えーっ、本当?僕たちは、もう友だちだね」「もちろん。ずっと前から友だちさ」と、カマキリは答えました。健ちゃんは嬉しくて嬉しくて、なかなか眠られませんでした。
翌日、健ちゃんは、カマキリを連れて学校に行きました。みんなが席につきました。「さあ、音楽会の始まりでーす」健ちゃんは今度こそと自信満々。でも、カマキリはタクトは振っても鳴いてはくれません。「ねえ、鳴いてよーっ!」
「嘘つき!健ちゃんの嘘つき。カマキリが鳴くわけないよ」「嘘つき、嘘つき!」「カブトムシだって鳴かないし、カマキリだって鳴くわけないよ」。みんな大騒ぎです。もう取り返しがつきません。
そのとき、幸子先生がニコニコと笑いながら「私は、健ちゃんが嘘つきだとは思いません。健ちゃんが聞いたという歌声を、みんなで聞きに行ってみましょう」と、助け舟を出してくれました。健ちゃんが先頭に立って、あのクスノキの根元まで来ました。すると、何処からともなく、あのピロピロピピピ・ピンコロピンコロリンというきれいな歌声が確かに聞こえてきました。「ほらねっ、嘘つきなんかじゃないよね」
「本当だ。聞こえる、聞こえる」みんな大喜びです。「でも、何の声だろう?」誰も答えることはできませんでした。カマキリは言いました。「ごめんなさい。鳴いたのは、私じゃあありません」。カブトムシも謝りました。「僕でもありませんでした」。
みんな代わる代わる木の幹に耳を押し付けて聞いています。「みなさん、これはね。このクスノキが森の話をしている声ですよ」と幸子先生が教えてくれました。「私も子供の頃、よく聞きに来ました」とニッコリ。「そうなんだ!この神様の木が歌っていたんだ」健ちゃんも、謎が解けてニッコリと笑いました。学校のみんなも、カブトムシもカマキリも顔を見合わせてニッコリと笑いました。
クスノキは生まれ育った頃の森で見たこと、聞いたことを話してくれました。森の虫や動物や子供たちと仲良く遊んだこと。リスもムササビもクスノキの枝で遊んだこと。小鳥たちがたくさんのかわいいかわいいヒナを育てたこと。親鳥の心配をよそに、次から次へと弱々しい羽ばたきで、大空へと巣立っていったこと。
幾時代かが過ぎて、いつの間にか人間の子供たちの笑い声が聞こえなくなったこと、外国の飛行機がいくつもいくつも落とした火の玉のこと、街が真っ赤に燃えたこと、何人もの人が泣きながら死んでいったこと。
やがて、鉄の機械がやってきて、トンネルやダムや車の走る道路ができたこと。そのために木々は切り倒され、谷に捨てられたこと。人間が植えた杉やヒノキが、息苦しさからか、悪い病気に罹ったこと。大風が吹き荒れ、洪水が起こり、森の形がすっかり変わってしまったこと。
それでも、再び子供たちが明るい声で歌い始めて、ほっとしたこと。心の優しい幸子先生や健ちゃんと出会い友だちになったこと。大きく息を吐きながら、ゆっくりゆっくりと聞かせてくれました。ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリン。その度に、辺りには涼やかに澄んだ空気が広がり、子供たちも幸子先生も、深く深く息を吸い込みました。
「健ちゃんって、すごい」「このクスノキと友だちなんだ」みんな声をそろえて叫びました。「ねえ?森の話を聞かせて」「もっともっと、森の話を聞かせて」。歌声はますます大きく、夕日に赤々と輝く山々に響きわたりました。
健ちゃんは、神様みたいなクスノキと友だちになったんです。もちろん学校のみんなとも仲のいい友だちです。カブトムシもカマキリも、森のみんなが友だちです。
「お母さん、僕、みんなと友だちになったよ。もう、寂しくなんかないよ」その晩、健ちゃんはお母さんに手紙を書きました。「お母さん、森には大きなクスノキが立っているんだよ。何でも見ていて、何でも知っていて、何でも話してくれる神様の木だから、お母さんの病気もきっと治してくれるよ。お母さん、早く良くなってね。僕、森が大好きだよ」
やがて新しい季節を迎えた頃、健ちゃんは、元気になって迎えに来たお母さんと、街に戻ることになりました。森のみんなが見送ってくれました。お母さんと一緒に神様の木にも「ありがとう」と「サヨナラ」を言いに行きました。クスノキは、ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリンといつものきれいな歌声を聞かせて見送ってくれました。「へーっ?お母さんも友だちだったんだ」「そうよ。私も子供の頃、このクスノキの話を何度も聞かせてもらったわ」と、お母さんも目に涙を浮かべながら、懐かしそうに聞いていました。「健ちゃんが生まれてきてくれた時にも、このクスノキに報告しに来たの。この木は何でも知っているのよ」。ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリン。
「ねえ?健ちゃん。森の話を聞かせて!」と、健ちゃんの友だちがやってきました。街に戻った健ちゃんは、半年暮らした森の話、神様の木から教えてもらった森の話を、クスノキにしてもらったのと同じようにゆっくりゆっくりと話しました。
街角のケヤキの木、学校や公園に立つドングリの木、秋に葉っぱの色を変える神社のイチョウの木、花や草や小さな鳥や虫たち。健ちゃんには、耳を澄ませば、どこにいても森の話が聞こえてきます。ピロピロピピピ・ピンコロピンコロリン。健ちゃんは、ますます森が好きになりました。
2021年07月31日
森への扉
その地下道は、学校への行き帰りに毎日通っているおなじみの道。出入り口の階段を下り、薄暗い角を直角に曲がったところに扉がありました。多分、ずーっとそこにあったのでしょうけど、あまり気にすることもありませんでしたので、健ちゃんは、はっきりとは覚えていませんでした。たとえ見ていたとしても、ペンキの禿げかかった鉄製の扉で、「掃除用具でもしまってあるのだろう」と、ちょっとした物入れくらいにしか思えない何の変哲もないような扉です。でも、その日健ちゃんが見たときには、扉の隙間から、太陽の光らしい明るい光がわずかに漏れていたのです。「あれっ?」と、少し気にはなったのですが、列を作って登校の途中でしたので、自分だけ立ち止まろうとはしませんでした。
その日は、一学期の最後の日。真夏の校庭では校長先生の話も聞いたし、教室に戻ってからは、成績表も渡され、夏休みの宿題もドッサリ。うんざりした気分で、あの扉のことを思い出すどころではありませんでした。
でも、学校からの帰り道、なぜか健ちゃんは一人きりで帰ることになりましたが、あの地下道まで来たときのことです。階段を一段か二段下りかかったとき、サーと涼しい風が健ちゃんを包みました。それどころか、ピーピーと数羽の小鳥がさえずりながら、頭の上を飛びすぎて行ったような気がしました。「おーっと」と、健ちゃんは頭をすくめましたが、とっさのことで何が起きたのか分かりません。
以前から地下道に入った途端、緑の匂いが広がったとか、野ウサギの親子が顔を出したという噂を聞いたことがありました。小川の流れる音が聞こえたという噂もありましたが、耳を澄ましても、上の道路を走りすぎる車のタイヤの音がうるさいだけで、そのことと、今起きていることとが結びつきません。
「どうしたの?何が起きたの?」と、健ちゃん。階段の下まで来たとき、今朝見たあの鉄の扉が、大きく開いているのが分かりました。「えー、嘘ーっ!」。扉の向こうに見えたのは、何と緑いっぱいの風景でした。「ここって、どこなの?」恐る恐る、扉の向こうに、一歩足を踏み入れてみました。夏休み前の暑さをすっかり忘れてしまいそうな、緑の香りいっぱいのさわやかな風が、またまた吹きすぎました。物入れだろうと思っていた扉の向こうには、高くて青い空と緑の木々の世界が広がっていました。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、枝や葉のざわめき・・・まるで別世界です。「ねえ?ここはどこ?」。
さらに一歩足を踏み出しました。何と、健ちゃんが顔を出したのは、大きな木の胴にぽっかりと空いた穴でした。「どこ?森?」
健ちゃんが木の穴から出ると、そこは去年の夏、お父さんやお母さんと出かけたキャンプ場によく似た森でした。名前も知らないいろんな種類の木々がたくさん茂り、小川が流れ、小さな池が広がり、「あれあれ?魚も跳ねてる」。
小川のせせらぎの音が聞こえ、枝や葉のざわめきの音が聞こえ、そこは何処から見ても森でした。「あれっ?」でも、少しだけ変なところがあります。木々の枝も、葉っぱも、絵に描いたようにきれいでしたが、どこか変なんです。「何か違うぞ!」と、健ちゃんが気づきました。「この葉っぱって、動いていない」「この枝って、揺れていない」「手だって濡れないし、この水も流れていないぞ」「魚は空中に止まったままだ」。そうです。健ちゃんが見たのは、紙に描かれた森だったのです。誰かが描いた森の絵だったのです。本物そっくりに、いや本物以上に上手に描かれていましたが、それらは全部、絵の具で描かれたニセモノ。「誰が描いているんだろう」と健ちゃん。
その時です。大きな丸まった紙を持って、茶色の野ウサギがやってきました。健ちゃんの姿を見つけると、軽く頭を下げ、「あっ、健ちゃん!忙しいんだから、ちょっと手伝って」と、手伝いの催促です。健ちゃんも、何がなんだか分からないまま、大きな紙の反対の端を持って、広げる手伝いを始めました。この絵では蝶や小鳥が飛んでいます。青空には、真っ白な雲がぽっかりと浮かんでいます。小川の魚は、水に戻って泳いでいます。先に広げてあった紙にぴったりと重ねるように、貼り付けました。
「あっ、健ちゃん、ありがとう」と、ウサギ。「いや、どういたしまして」と健ちゃん。「君は誰?何で僕の名前を知っているの?」と聞いてみました。ウサギは、それには答えず、いそいそと奥の方に行ったかと思うと、またまた丸めた紙を持って、やって来ました。「さあ、健ちゃん、今度はこれ」と、健ちゃんに命令です。健ちゃんは答えも聞けずに、紙の端を持って走りました。今度の絵では、入道雲がモクモクと高く高く昇っています。「そこに、電気のスイッチがあるから、少し暗くして」と、ウサギが言いました。足元に電気のコンセントがたくさん並んでいて、健ちゃんは、その中のいくつかを抜きました。「それじゃあ、暗すぎるよ。忙しいんだから、もっと考えてくれなくっちゃあ」と、丸い目をキョロキョロさせたウサギに叱られてしまいました。
ウサギは、早くも次の絵を広げ始めています。「さあ、引っ張って、引っ張って」。とうとう絵の中では、夕立が降り始め、雷も光り始めました。「そこのスイッチを入れたり切ったりして」と、言われるままにカチカチやると、電気が点いたり消えたりして、本物の稲妻のようです。「シャワーのコックも回して」。今度は雨が降り始めました。「音、音。音を忘れているよ」と、ウサギは大きな太鼓をドンドンドンドドドドドンと叩き始めました。
一体、何が起きたのでしょう。「ねえ、ちょっと待ってよ」と、健ちゃんはウサギを止めました。「うん。でも、今が一番難しいところなんだ。これを広げてからにして」と、ピシャリと言われ、素直な健ちゃんは言われるままに、手伝いました。「わー、きれい」。今度は、空に大きな虹が架かった絵です。「電気、電気」と、言われ、一つずつコンセントを差し込みました。「そうそう、いい感じ」。空は次第に明るさをまし、七色の虹もだんだんとうすくなっていきました。森の緑は雨に濡れて、キラキラと光っています。雨上がりの森の美しさは、言葉では言い表せないほどです。
「はい、お待たせ。健ちゃんの質問は、何だったっけ?」。「君は、誰?」と、健ちゃんは、もう一度尋ねました。「それは、僕にも分からない。もう何年も前から、この仕事をしているんだ。美しい森を守る、大切な仕事さ」と、ウサギは答えました。「じゃあ、僕の名前をどうして知ってるの?」と、健ちゃん。「だって、去年の夏にキャンプを楽しみに来たじゃない」と、ウサギは答えました。「えー?だって、あれは森だよ?」。「だから、ここが森じゃん」と、ウサギ。
確かに、健ちゃんも、去年の夏に遊んだ森にそっくりだとは思いましたが、でも、キャンプを楽しんだ森へは、車で何時間か走って、やっとたどり着いたのです。こんな地下道の扉から来たわけではありません。「それに池では魚釣りも楽しんだし、夜には枝を集めてキャンプファイアーだってしたんだよ。クワガタ探しもしたし、木登りだってしたんだよ。ここは似ているけど、こんなのって本当の森なんかじゃあないよ」と、大きな声で言いました。ウサギは、ちょっと困ったような顔をして「僕だって、僕なりに一生懸命描いているんだけど、まだあまり上手くないかも知れない。でも、健ちゃんが来たのは、確かに僕の森なんだ」と、ボソボソと話し始めました。
「健ちゃんたちが考えているような本当の森なんて、もう何年も前からどこにもないんだよ。山に行っても、広い道路が作られ、車が走り、木が切り倒され、ダムができ、都会と同じような店が並び、夜も明るい電気がともり、コンビニだってあるんだよ。健ちゃんたちが美しいと感じるような森は、全部、僕の仲間が描いた森なんだ。池や川には魚がいた方がいいだろう?クワガタや蝶が棲む森の方がいいだろう?木の葉がキラキラ輝き、涼しい風が吹き、小鳥がさえずり、きれいな虹だって見たいし、真っ赤な夕焼けだって見たいんだろう?だったら、そんな森は、もうどこにもないんだよ。僕は自分が誰かも知らないけど、この美しい森を守るのが、僕たち仲間の仕事なんだ」と、一気に話しました。
健ちゃんも、ちょっと考えて話しました。「でも、こんなのって本当の森じゃあないよ。こんなことしても、本当の森や自然を守っていることにはならないよ。確かにきれいだけど、空だって雲だって虹だって、君が描いたニセモノだし、木だって魚だって生きてないじゃん。それに、ここは森じゃあなくて、地下道の中じゃん。道路の下じゃん。森なんかじゃあない!」
「じゃあ、本当の森って、どこにあるの?誰が守るの?健ちゃんが、守るの?」ウサギは、長い耳をピクピクさせて話しました。「そ、それは」と、とっさに健ちゃんは答えました。「僕が守るよ。だから君も、自分が誰かを思い出してほしい。よければ僕の友達になってほしい。一緒に森を守ろうよ」。
ウサギは「さあ、そろそろ夕方の準備の時間だよ。健ちゃんも手伝ってくれるね。」と、大きな扇風機を持ち出しました。「そうか。さっきの涼しい風は、この扇風機の風だったんだ」。ウサギが丸めた紙を広げ始めました。健ちゃんも、手伝いました。山が燃えるような真っ赤な夕焼けの空が描かれていました。鳥がねぐらに帰ろうとしています。「それは折り紙?さっき小鳥だと思ったのは、これだったの?風の音も水の音も小鳥のさえずりも、CDなの?緑の香りって、もしかしたら、この芳香剤?やっぱり、これじゃあダメだよ。まるでTVゲームと同じじゃないか。本当の森を、僕たちで守ろう!」と、健ちゃんは決心しました。ウサギも鼻をモグモグさせて小さくうなずきました。
「今日は、これで帰るけど、明日また来るから。いろいろ教えてね」と、健ちゃんが、帰ろうとすると、ウサギが初めてニッコリと笑いました。「うん、森を守るっていうこと。約束だよ」と、ウサギは、ドングリの実を5つ、健ちゃんに渡しました。「森の恵みだね」と、健ちゃんは思いました。「じゃあ、また明日」「うん、じゃあ。ああ、それから、君は野ウサギだよ。それも、かなり可愛い野ウサギだよ。覚えておいてね」。健ちゃんはウサギの手を軽く握りました。
健ちゃんは、木の穴に戻りました。扉を開けると、そこは、いつもの地下道です。健ちゃんは、鉄の扉をきっちりと閉めました。また、いつもの蒸し暑い地下道に逆戻りです。健ちゃんは、絵の世界でもいいから、さっきの森に戻りたいと、少し思いましたが、「でも、あれは本当の森じゃあない」と、思い返しました。「僕は森を守るために、何ができるかを考えるぞ」と、つぶやきました。ふと、手の中を見ると、健ちゃんの手のひらには、ウサギに渡された5つのドングリが確かに握られていました。
その翌日の朝、健ちゃんは、あの地下道にやってきました。階段を下りて、鉄の扉を探しました。でも、どこにも見当たりませんでした。健ちゃんがそこに見つけたのは、一枚の張り紙でした。「健ちゃん、約束を忘れないでね。かなり可愛い野ウサギより」と、書いてありました。健ちゃんは、ドングリの実を握り締めました。ウサギとの約束は必ず守ろう、と思いました。
今年の夏休みも、健ちゃんの家族は、森にキャンプ遊びに出かけました。そこには、地下道にあった、森への扉の中で見たのとそっくりな景色が広がっていました。「いい天気で良かったね」と、お母さんが言いました。健ちゃんには、この後起こりそうなことが何のとなく予測できましたので、「でも、もうじき雨が降って、雷も鳴るよ」と言いました。「えっ?まさか」と、お父さんが言いました。やがて健ちゃんの言った通り、夕立が降って、雨上りにはきれいな虹も架かりました。健ちゃんは、野ウサギのことを思い出しました。「もしかしたら」と、少し不安になった健ちゃんが手を入れてみると、小川にはサラサラと冷たい水が流れていました。「本物だ」池には魚が跳ねています。森の空気を思いっきり深呼吸してみました。「全部本物だよね。まだ、間に合いそうだな」と、ウサギにもらった5個のドングリの実をそっと埋めて、丁寧に土をかけました。山は夕焼けで真っ赤に染まりました。
「約束だもんね」。健ちゃんは、野ウサギとの約束を忘れませんでした。いつか、健ちゃんが埋めたドングリが大きな木に育つでしょう。美しい森は、もっともっと美しくなるでしょう。ウサギと彼の仲間が、必死で守ろうとしていた森が、今、目の前で息づいています。健ちゃんは、画用紙を取り出して、夕焼けの森の絵を描きました。「ウサギさんみたいには、上手く描けないけどね」。絵の右下に、あのウサギも描きました。ちょっと生意気なかなり可愛い野ウサギが笑っています。「よし。僕が、森を守る!」と、健ちゃんは力強くつぶやきました。
その日は、一学期の最後の日。真夏の校庭では校長先生の話も聞いたし、教室に戻ってからは、成績表も渡され、夏休みの宿題もドッサリ。うんざりした気分で、あの扉のことを思い出すどころではありませんでした。
でも、学校からの帰り道、なぜか健ちゃんは一人きりで帰ることになりましたが、あの地下道まで来たときのことです。階段を一段か二段下りかかったとき、サーと涼しい風が健ちゃんを包みました。それどころか、ピーピーと数羽の小鳥がさえずりながら、頭の上を飛びすぎて行ったような気がしました。「おーっと」と、健ちゃんは頭をすくめましたが、とっさのことで何が起きたのか分かりません。
以前から地下道に入った途端、緑の匂いが広がったとか、野ウサギの親子が顔を出したという噂を聞いたことがありました。小川の流れる音が聞こえたという噂もありましたが、耳を澄ましても、上の道路を走りすぎる車のタイヤの音がうるさいだけで、そのことと、今起きていることとが結びつきません。
「どうしたの?何が起きたの?」と、健ちゃん。階段の下まで来たとき、今朝見たあの鉄の扉が、大きく開いているのが分かりました。「えー、嘘ーっ!」。扉の向こうに見えたのは、何と緑いっぱいの風景でした。「ここって、どこなの?」恐る恐る、扉の向こうに、一歩足を踏み入れてみました。夏休み前の暑さをすっかり忘れてしまいそうな、緑の香りいっぱいのさわやかな風が、またまた吹きすぎました。物入れだろうと思っていた扉の向こうには、高くて青い空と緑の木々の世界が広がっていました。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、枝や葉のざわめき・・・まるで別世界です。「ねえ?ここはどこ?」。
さらに一歩足を踏み出しました。何と、健ちゃんが顔を出したのは、大きな木の胴にぽっかりと空いた穴でした。「どこ?森?」
健ちゃんが木の穴から出ると、そこは去年の夏、お父さんやお母さんと出かけたキャンプ場によく似た森でした。名前も知らないいろんな種類の木々がたくさん茂り、小川が流れ、小さな池が広がり、「あれあれ?魚も跳ねてる」。
小川のせせらぎの音が聞こえ、枝や葉のざわめきの音が聞こえ、そこは何処から見ても森でした。「あれっ?」でも、少しだけ変なところがあります。木々の枝も、葉っぱも、絵に描いたようにきれいでしたが、どこか変なんです。「何か違うぞ!」と、健ちゃんが気づきました。「この葉っぱって、動いていない」「この枝って、揺れていない」「手だって濡れないし、この水も流れていないぞ」「魚は空中に止まったままだ」。そうです。健ちゃんが見たのは、紙に描かれた森だったのです。誰かが描いた森の絵だったのです。本物そっくりに、いや本物以上に上手に描かれていましたが、それらは全部、絵の具で描かれたニセモノ。「誰が描いているんだろう」と健ちゃん。
その時です。大きな丸まった紙を持って、茶色の野ウサギがやってきました。健ちゃんの姿を見つけると、軽く頭を下げ、「あっ、健ちゃん!忙しいんだから、ちょっと手伝って」と、手伝いの催促です。健ちゃんも、何がなんだか分からないまま、大きな紙の反対の端を持って、広げる手伝いを始めました。この絵では蝶や小鳥が飛んでいます。青空には、真っ白な雲がぽっかりと浮かんでいます。小川の魚は、水に戻って泳いでいます。先に広げてあった紙にぴったりと重ねるように、貼り付けました。
「あっ、健ちゃん、ありがとう」と、ウサギ。「いや、どういたしまして」と健ちゃん。「君は誰?何で僕の名前を知っているの?」と聞いてみました。ウサギは、それには答えず、いそいそと奥の方に行ったかと思うと、またまた丸めた紙を持って、やって来ました。「さあ、健ちゃん、今度はこれ」と、健ちゃんに命令です。健ちゃんは答えも聞けずに、紙の端を持って走りました。今度の絵では、入道雲がモクモクと高く高く昇っています。「そこに、電気のスイッチがあるから、少し暗くして」と、ウサギが言いました。足元に電気のコンセントがたくさん並んでいて、健ちゃんは、その中のいくつかを抜きました。「それじゃあ、暗すぎるよ。忙しいんだから、もっと考えてくれなくっちゃあ」と、丸い目をキョロキョロさせたウサギに叱られてしまいました。
ウサギは、早くも次の絵を広げ始めています。「さあ、引っ張って、引っ張って」。とうとう絵の中では、夕立が降り始め、雷も光り始めました。「そこのスイッチを入れたり切ったりして」と、言われるままにカチカチやると、電気が点いたり消えたりして、本物の稲妻のようです。「シャワーのコックも回して」。今度は雨が降り始めました。「音、音。音を忘れているよ」と、ウサギは大きな太鼓をドンドンドンドドドドドンと叩き始めました。
一体、何が起きたのでしょう。「ねえ、ちょっと待ってよ」と、健ちゃんはウサギを止めました。「うん。でも、今が一番難しいところなんだ。これを広げてからにして」と、ピシャリと言われ、素直な健ちゃんは言われるままに、手伝いました。「わー、きれい」。今度は、空に大きな虹が架かった絵です。「電気、電気」と、言われ、一つずつコンセントを差し込みました。「そうそう、いい感じ」。空は次第に明るさをまし、七色の虹もだんだんとうすくなっていきました。森の緑は雨に濡れて、キラキラと光っています。雨上がりの森の美しさは、言葉では言い表せないほどです。
「はい、お待たせ。健ちゃんの質問は、何だったっけ?」。「君は、誰?」と、健ちゃんは、もう一度尋ねました。「それは、僕にも分からない。もう何年も前から、この仕事をしているんだ。美しい森を守る、大切な仕事さ」と、ウサギは答えました。「じゃあ、僕の名前をどうして知ってるの?」と、健ちゃん。「だって、去年の夏にキャンプを楽しみに来たじゃない」と、ウサギは答えました。「えー?だって、あれは森だよ?」。「だから、ここが森じゃん」と、ウサギ。
確かに、健ちゃんも、去年の夏に遊んだ森にそっくりだとは思いましたが、でも、キャンプを楽しんだ森へは、車で何時間か走って、やっとたどり着いたのです。こんな地下道の扉から来たわけではありません。「それに池では魚釣りも楽しんだし、夜には枝を集めてキャンプファイアーだってしたんだよ。クワガタ探しもしたし、木登りだってしたんだよ。ここは似ているけど、こんなのって本当の森なんかじゃあないよ」と、大きな声で言いました。ウサギは、ちょっと困ったような顔をして「僕だって、僕なりに一生懸命描いているんだけど、まだあまり上手くないかも知れない。でも、健ちゃんが来たのは、確かに僕の森なんだ」と、ボソボソと話し始めました。
「健ちゃんたちが考えているような本当の森なんて、もう何年も前からどこにもないんだよ。山に行っても、広い道路が作られ、車が走り、木が切り倒され、ダムができ、都会と同じような店が並び、夜も明るい電気がともり、コンビニだってあるんだよ。健ちゃんたちが美しいと感じるような森は、全部、僕の仲間が描いた森なんだ。池や川には魚がいた方がいいだろう?クワガタや蝶が棲む森の方がいいだろう?木の葉がキラキラ輝き、涼しい風が吹き、小鳥がさえずり、きれいな虹だって見たいし、真っ赤な夕焼けだって見たいんだろう?だったら、そんな森は、もうどこにもないんだよ。僕は自分が誰かも知らないけど、この美しい森を守るのが、僕たち仲間の仕事なんだ」と、一気に話しました。
健ちゃんも、ちょっと考えて話しました。「でも、こんなのって本当の森じゃあないよ。こんなことしても、本当の森や自然を守っていることにはならないよ。確かにきれいだけど、空だって雲だって虹だって、君が描いたニセモノだし、木だって魚だって生きてないじゃん。それに、ここは森じゃあなくて、地下道の中じゃん。道路の下じゃん。森なんかじゃあない!」
「じゃあ、本当の森って、どこにあるの?誰が守るの?健ちゃんが、守るの?」ウサギは、長い耳をピクピクさせて話しました。「そ、それは」と、とっさに健ちゃんは答えました。「僕が守るよ。だから君も、自分が誰かを思い出してほしい。よければ僕の友達になってほしい。一緒に森を守ろうよ」。
ウサギは「さあ、そろそろ夕方の準備の時間だよ。健ちゃんも手伝ってくれるね。」と、大きな扇風機を持ち出しました。「そうか。さっきの涼しい風は、この扇風機の風だったんだ」。ウサギが丸めた紙を広げ始めました。健ちゃんも、手伝いました。山が燃えるような真っ赤な夕焼けの空が描かれていました。鳥がねぐらに帰ろうとしています。「それは折り紙?さっき小鳥だと思ったのは、これだったの?風の音も水の音も小鳥のさえずりも、CDなの?緑の香りって、もしかしたら、この芳香剤?やっぱり、これじゃあダメだよ。まるでTVゲームと同じじゃないか。本当の森を、僕たちで守ろう!」と、健ちゃんは決心しました。ウサギも鼻をモグモグさせて小さくうなずきました。
「今日は、これで帰るけど、明日また来るから。いろいろ教えてね」と、健ちゃんが、帰ろうとすると、ウサギが初めてニッコリと笑いました。「うん、森を守るっていうこと。約束だよ」と、ウサギは、ドングリの実を5つ、健ちゃんに渡しました。「森の恵みだね」と、健ちゃんは思いました。「じゃあ、また明日」「うん、じゃあ。ああ、それから、君は野ウサギだよ。それも、かなり可愛い野ウサギだよ。覚えておいてね」。健ちゃんはウサギの手を軽く握りました。
健ちゃんは、木の穴に戻りました。扉を開けると、そこは、いつもの地下道です。健ちゃんは、鉄の扉をきっちりと閉めました。また、いつもの蒸し暑い地下道に逆戻りです。健ちゃんは、絵の世界でもいいから、さっきの森に戻りたいと、少し思いましたが、「でも、あれは本当の森じゃあない」と、思い返しました。「僕は森を守るために、何ができるかを考えるぞ」と、つぶやきました。ふと、手の中を見ると、健ちゃんの手のひらには、ウサギに渡された5つのドングリが確かに握られていました。
その翌日の朝、健ちゃんは、あの地下道にやってきました。階段を下りて、鉄の扉を探しました。でも、どこにも見当たりませんでした。健ちゃんがそこに見つけたのは、一枚の張り紙でした。「健ちゃん、約束を忘れないでね。かなり可愛い野ウサギより」と、書いてありました。健ちゃんは、ドングリの実を握り締めました。ウサギとの約束は必ず守ろう、と思いました。
今年の夏休みも、健ちゃんの家族は、森にキャンプ遊びに出かけました。そこには、地下道にあった、森への扉の中で見たのとそっくりな景色が広がっていました。「いい天気で良かったね」と、お母さんが言いました。健ちゃんには、この後起こりそうなことが何のとなく予測できましたので、「でも、もうじき雨が降って、雷も鳴るよ」と言いました。「えっ?まさか」と、お父さんが言いました。やがて健ちゃんの言った通り、夕立が降って、雨上りにはきれいな虹も架かりました。健ちゃんは、野ウサギのことを思い出しました。「もしかしたら」と、少し不安になった健ちゃんが手を入れてみると、小川にはサラサラと冷たい水が流れていました。「本物だ」池には魚が跳ねています。森の空気を思いっきり深呼吸してみました。「全部本物だよね。まだ、間に合いそうだな」と、ウサギにもらった5個のドングリの実をそっと埋めて、丁寧に土をかけました。山は夕焼けで真っ赤に染まりました。
「約束だもんね」。健ちゃんは、野ウサギとの約束を忘れませんでした。いつか、健ちゃんが埋めたドングリが大きな木に育つでしょう。美しい森は、もっともっと美しくなるでしょう。ウサギと彼の仲間が、必死で守ろうとしていた森が、今、目の前で息づいています。健ちゃんは、画用紙を取り出して、夕焼けの森の絵を描きました。「ウサギさんみたいには、上手く描けないけどね」。絵の右下に、あのウサギも描きました。ちょっと生意気なかなり可愛い野ウサギが笑っています。「よし。僕が、森を守る!」と、健ちゃんは力強くつぶやきました。
2021年07月30日
修平さんの紙飛行機
今日は朝からポカポカの上天気。子供たちは、公園の広場に集まって遊んでいました。和くんも「空飛ぶコーギー」のマロンもその中にいました。車椅子の健ちゃんの姿も見えます。誰かが、紙飛行機で遊び始めました。和くんたちも紙飛行機を折りました。ロケットみたいに尖らせたり、尾羽根を立てたり、それぞれ工夫を凝らして、遠くに飛ばそうと一生懸命です。飛び回る白い紙飛行機を追いかけるようにマロンも空を飛んでいます。健ちゃんも車椅子を押してくれるお姉ちゃんの陽ちゃんに手伝ってもらい、力いっぱい紙飛行機を飛ばしました。大きな羽根の三角形の飛行機は、穏やかな風に載り、フワリフワリと弧を描きながら、広場の反対の小道まで飛んでいきました。わーい、わーい!
修平おじいさんが杖を突きながら公園の小道に差し掛かったのは、ちょうど、その時でした。修平さんは、その紙飛行機を見上げると、エイとばかりに手にした杖ではたき落としました。子供たちは、ビックリしました。陽ちゃんが紙飛行機に駆け寄りました。「ごめんなさい。ご迷惑をかけました」と、修平おじいさんに謝りました。修平さんは何も答えずに広場の中に入ってきました。広場では、子供たちの紙飛行機がいくつもいくつも飛んでいました。
修平さんは、その紙飛行機に近づいて、さっきと同じように一つ一つ、杖を振り上げてははたき落としました。子供たちは、黙って自分の紙飛行機を拾いました。空を飛んでいたマロンも驚いて降りてきました。修平おじいさんは低い小さな声で「飛行機を飛ばすのは、やめなさい」とつぶやくように言いました。最後まで飛んでいた和くんの紙飛行機にも、修平さんの杖が鋭く振り下ろされました。マロンがワンワンと吠えました。その声に驚いたように、修平さんの杖が空を切りました。グラっと傾き、修平おじいさんの体が広場の土の上に倒れました。
健ちゃんの車椅子が真っ先に駆けつけました。続いてマロンが駆け寄りました。和くんが、修平おじいさんに「大丈夫ですか?」と声をかけ、抱き起こしました。修平さんの頬は広場の土と涙で汚れていました。「すまんな。大人気ないことをしてしまった」と修平さんは言いました。「ワシは、昔、日本が戦争をしていた頃、飛行機に乗っていたことがあってなあ」と、胡坐をかいて話し始めました。
いつの間にか、子供たちが心配そうに集まってきました。「ワシの仲間たちは、飛行機に乗って、泣きながら海の中に消えて行ったんだ」と、修平おじいさんの話に耳を傾けました。「人間は鳥や昆虫じゃあないんだ。だから空を飛ぶなんて、してはいけないことなんじゃあないかって思うな。飛べもしない人間が、空を飛んで、何人も何人も死んでいった。死ぬためだけに飛んで行ったんだよ。飛べもしない人間がね」と、修平さんは大きなため息をつきました。「ワシは何もできずに仲間を見送って以来、飛行機が憎くて憎くて」と、子供たちを見回しました。その目には、暖かい涙が光っていました。マロンにも、修平おじいさんの気持ちがよく分かりました。
「君たちも、おじいちゃんやおばあちゃんに聞いてごらん。黒くて大きな飛行機に追い回されて、暗い穴の中で息を潜めていた頃の話を」と、修平さんは続けました。「そりゃあ、怖かったさ。家々が焼かれて、服が焼かれて、熱い熱いと死んでいった人が、どれほどいたことか。みんな、飛行機が震えるほど怖かったんだ」。修平おじいさんの周りには、マロンの仲間たちも集まって来ました。トイ・プードルのキャンディーもラブラドールも集まって来ました。
「でもね。この子たちが、そんな世界を変えてくれるのよ」と、里子おばあちゃんの声がしました。和くんが振り返りました。マロンは嬉しくて、おばあちゃんの車椅子に駆け寄りました。
「修平さん。あなたの言いたいことはよく分かるけど、それは、この子たちが悪いんじゃあないわ。子供たちの紙飛行機は、子供たちの夢を乗せているのよ。マロンちゃんだって、ママに会いたくって、空を飛んだのよ。夢を持つってことは、素晴らしいことだと思うわ」と、里子おばあちゃんが言いました。「そう言う里子さんの夢って何なんだ?」と修平さんが聞きました。「私の夢?私の夢はね、こうして可愛いマロンちゃんや子供たちに会って、いっぱいお話することかな」と里子おばあちゃんは答えました。
里子おばあちゃんが上着のポケットに手を入れました。「さあ、みんなで食べましょう」と、黄色いミカンを出しました。それを見て、修平おじいさんも「いやあ、実はワシも」と、同じようにポケットをゴソゴソやってミカンを取り出しました。「さあ、子供たちも、一緒にミカンを食べようか」と、恥ずかしそうに言いました。和くんが手を出しました。陽ちゃんも一つ受け取り、皮を剥いて二つに割りました。次々と子供たちの手が伸びました。里子おばあちゃんはマロンにミカンを半分あげました。トイ・プードルのキャンディーはマロンのミカンを分けてもらいました。みんな、みんな、ミカンを口に入れて、甘酸っぱさを感じていました。
「みんなで分けて食べるミカンって、本当に美味しいね」と、修平おじいさんが言いました。みんなが大きくうなずきました。「そうか。紙飛行機は子供たちの夢を乗せて飛んでいるのか」と、修平さんが、真っ白な紙飛行機を空に向けて飛ばしました。公園のハトたちが、紙飛行機を取り巻きました。マロンが駆け出しました。短い足が地面を蹴って、空へと飛び上がりました。「おお、マロン。ワシの代わりに飛んでくれ!ワシの夢は、マロンの夢と同じさ。いつか、ママに会いに行きたいんだよ」と、修平おじいさんは笑いながら言いました。子供たちの紙飛行機が修平おじいさんの夢を乗せて、一斉に空へと舞い上がりました。
修平おじいさんが杖を突きながら公園の小道に差し掛かったのは、ちょうど、その時でした。修平さんは、その紙飛行機を見上げると、エイとばかりに手にした杖ではたき落としました。子供たちは、ビックリしました。陽ちゃんが紙飛行機に駆け寄りました。「ごめんなさい。ご迷惑をかけました」と、修平おじいさんに謝りました。修平さんは何も答えずに広場の中に入ってきました。広場では、子供たちの紙飛行機がいくつもいくつも飛んでいました。
修平さんは、その紙飛行機に近づいて、さっきと同じように一つ一つ、杖を振り上げてははたき落としました。子供たちは、黙って自分の紙飛行機を拾いました。空を飛んでいたマロンも驚いて降りてきました。修平おじいさんは低い小さな声で「飛行機を飛ばすのは、やめなさい」とつぶやくように言いました。最後まで飛んでいた和くんの紙飛行機にも、修平さんの杖が鋭く振り下ろされました。マロンがワンワンと吠えました。その声に驚いたように、修平さんの杖が空を切りました。グラっと傾き、修平おじいさんの体が広場の土の上に倒れました。
健ちゃんの車椅子が真っ先に駆けつけました。続いてマロンが駆け寄りました。和くんが、修平おじいさんに「大丈夫ですか?」と声をかけ、抱き起こしました。修平さんの頬は広場の土と涙で汚れていました。「すまんな。大人気ないことをしてしまった」と修平さんは言いました。「ワシは、昔、日本が戦争をしていた頃、飛行機に乗っていたことがあってなあ」と、胡坐をかいて話し始めました。
いつの間にか、子供たちが心配そうに集まってきました。「ワシの仲間たちは、飛行機に乗って、泣きながら海の中に消えて行ったんだ」と、修平おじいさんの話に耳を傾けました。「人間は鳥や昆虫じゃあないんだ。だから空を飛ぶなんて、してはいけないことなんじゃあないかって思うな。飛べもしない人間が、空を飛んで、何人も何人も死んでいった。死ぬためだけに飛んで行ったんだよ。飛べもしない人間がね」と、修平さんは大きなため息をつきました。「ワシは何もできずに仲間を見送って以来、飛行機が憎くて憎くて」と、子供たちを見回しました。その目には、暖かい涙が光っていました。マロンにも、修平おじいさんの気持ちがよく分かりました。
「君たちも、おじいちゃんやおばあちゃんに聞いてごらん。黒くて大きな飛行機に追い回されて、暗い穴の中で息を潜めていた頃の話を」と、修平さんは続けました。「そりゃあ、怖かったさ。家々が焼かれて、服が焼かれて、熱い熱いと死んでいった人が、どれほどいたことか。みんな、飛行機が震えるほど怖かったんだ」。修平おじいさんの周りには、マロンの仲間たちも集まって来ました。トイ・プードルのキャンディーもラブラドールも集まって来ました。
「でもね。この子たちが、そんな世界を変えてくれるのよ」と、里子おばあちゃんの声がしました。和くんが振り返りました。マロンは嬉しくて、おばあちゃんの車椅子に駆け寄りました。
「修平さん。あなたの言いたいことはよく分かるけど、それは、この子たちが悪いんじゃあないわ。子供たちの紙飛行機は、子供たちの夢を乗せているのよ。マロンちゃんだって、ママに会いたくって、空を飛んだのよ。夢を持つってことは、素晴らしいことだと思うわ」と、里子おばあちゃんが言いました。「そう言う里子さんの夢って何なんだ?」と修平さんが聞きました。「私の夢?私の夢はね、こうして可愛いマロンちゃんや子供たちに会って、いっぱいお話することかな」と里子おばあちゃんは答えました。
里子おばあちゃんが上着のポケットに手を入れました。「さあ、みんなで食べましょう」と、黄色いミカンを出しました。それを見て、修平おじいさんも「いやあ、実はワシも」と、同じようにポケットをゴソゴソやってミカンを取り出しました。「さあ、子供たちも、一緒にミカンを食べようか」と、恥ずかしそうに言いました。和くんが手を出しました。陽ちゃんも一つ受け取り、皮を剥いて二つに割りました。次々と子供たちの手が伸びました。里子おばあちゃんはマロンにミカンを半分あげました。トイ・プードルのキャンディーはマロンのミカンを分けてもらいました。みんな、みんな、ミカンを口に入れて、甘酸っぱさを感じていました。
「みんなで分けて食べるミカンって、本当に美味しいね」と、修平おじいさんが言いました。みんなが大きくうなずきました。「そうか。紙飛行機は子供たちの夢を乗せて飛んでいるのか」と、修平さんが、真っ白な紙飛行機を空に向けて飛ばしました。公園のハトたちが、紙飛行機を取り巻きました。マロンが駆け出しました。短い足が地面を蹴って、空へと飛び上がりました。「おお、マロン。ワシの代わりに飛んでくれ!ワシの夢は、マロンの夢と同じさ。いつか、ママに会いに行きたいんだよ」と、修平おじいさんは笑いながら言いました。子供たちの紙飛行機が修平おじいさんの夢を乗せて、一斉に空へと舞い上がりました。
2021年07月29日
整理整頓
ポメラニアンのポテトの小屋には、小さな箱、大きな箱、小さな缶、大きな缶がいっぱい積まれていました。ポテトに言わせれば、「これは、クリスマスツリーとか冬に使うものでしょう。これは、沙織さんにもらったもの。来年用の野菜の種はこの缶にしまっておいて、腹ペコマロンが来た時には、この缶の中に、少しだけドッグフードが入ってる」。つまり、整理整頓。空いたところはきれいにお掃除をしています。血液型はA型かな?
「ポテチはどうして、そんなにきれいにしてるの?」と、コーギーのマロンが聞きました。「だって、きれいにした方が見つけやすいし、気持ちだっていいじゃん。むしろ、きちんとしていない方が、気持ち悪くなっちゃう」と、ポテトが答えました。「ええ?そんなのって、窮屈じゃない?」。「全然!野菜だって、毎年の記録を残して来年に役立てるんだ。種を蒔く時期とかね。僕はカレンダーとか分からないから、初めてツバメが来た日とか、セミが鳴いた日とか」と、ポテトが言いました。「朝は、きまった時間に起きて、マロンと遊ぶ時以外は、食事だって時間通りにしてるよ」。「そういえば、ポテチって間食とかあまりしないよね」と、マロンが言いました。「そう、マロンみたいに拾い食いとかもしない」。「たいしたもんだ。来年、1年生になれそうだね」。
「マロン。この前の石ころで遊ぼう」と、ポテトが言いました。「この前?いつ?」と、マロンが聞きました。「3日前の公園で石蹴りして遊んだじゃん」「さあ?その石って、僕が持ってるの?」「だって、マロンが蹴りながら帰ったよ」「じゃあ、どこかその辺にあるんじゃない?」「その辺って、どの辺?」「その辺は、その辺…」「ちゃんとしておかないからだよ!」。
「じゃあ、電車ごっこの紐はどうした?」と、ポテトが聞きました。「電車ごっこ?ああ、あれね。あれは…」「どこにあるの?」「ポテチが持ってない?」「マロンが首に巻いて帰ったでしょう?」「じゃあ、どこかその辺にあるんじゃない?」「その辺って、どの辺?」「その辺は、その辺…」「もう、ちゃんと片付けないからだよ!」。
マロンときたら、小屋の中はグチャグチャ。何でもかんでも捨てられずにとっておくくせに、山積みのまま。新しいものが上に重なり、また新しいものがその上に。やがては雪崩のように崩れて下敷きになり、やっと這い出してまた上に物を置く。もう、どこに何をしまったのか、まったく覚えていません。おまけに朝寝坊で食いしん坊で、忘れん坊。それでも、他のことは忘れても夢だけは忘れないし、優しいし、空を飛べるし…。もしかしたら、O型かな?
「ポテチはどうして、そんなにきれいにしてるの?」と、コーギーのマロンが聞きました。「だって、きれいにした方が見つけやすいし、気持ちだっていいじゃん。むしろ、きちんとしていない方が、気持ち悪くなっちゃう」と、ポテトが答えました。「ええ?そんなのって、窮屈じゃない?」。「全然!野菜だって、毎年の記録を残して来年に役立てるんだ。種を蒔く時期とかね。僕はカレンダーとか分からないから、初めてツバメが来た日とか、セミが鳴いた日とか」と、ポテトが言いました。「朝は、きまった時間に起きて、マロンと遊ぶ時以外は、食事だって時間通りにしてるよ」。「そういえば、ポテチって間食とかあまりしないよね」と、マロンが言いました。「そう、マロンみたいに拾い食いとかもしない」。「たいしたもんだ。来年、1年生になれそうだね」。
「マロン。この前の石ころで遊ぼう」と、ポテトが言いました。「この前?いつ?」と、マロンが聞きました。「3日前の公園で石蹴りして遊んだじゃん」「さあ?その石って、僕が持ってるの?」「だって、マロンが蹴りながら帰ったよ」「じゃあ、どこかその辺にあるんじゃない?」「その辺って、どの辺?」「その辺は、その辺…」「ちゃんとしておかないからだよ!」。
「じゃあ、電車ごっこの紐はどうした?」と、ポテトが聞きました。「電車ごっこ?ああ、あれね。あれは…」「どこにあるの?」「ポテチが持ってない?」「マロンが首に巻いて帰ったでしょう?」「じゃあ、どこかその辺にあるんじゃない?」「その辺って、どの辺?」「その辺は、その辺…」「もう、ちゃんと片付けないからだよ!」。
マロンときたら、小屋の中はグチャグチャ。何でもかんでも捨てられずにとっておくくせに、山積みのまま。新しいものが上に重なり、また新しいものがその上に。やがては雪崩のように崩れて下敷きになり、やっと這い出してまた上に物を置く。もう、どこに何をしまったのか、まったく覚えていません。おまけに朝寝坊で食いしん坊で、忘れん坊。それでも、他のことは忘れても夢だけは忘れないし、優しいし、空を飛べるし…。もしかしたら、O型かな?
2021年07月28日
ムシャムシャ
ムシャムシャ。ある朝、コーギーの耳にムシャムシャ食べる音が聞こえました。「ああ、誰かが何かを食べてるな」と、小さな音でしたが、マロンにはすぐに分かりました。でも「誰が?何を?」。マロンはあちこち見回してみました。「カブトムシ?ツクツクホウシ?」。「僕らは、木の蜜しか吸わないよ」。「モンシロチョウ?シジミチョウ?」「私たちは、花の蜜しか吸わないわ」。でも、ムシャムシャ食べる音は、ますます大きく響きました。
「誰が?何を?」。マロンが見つけたレモンの葉っぱが、誰かに食べられていました。コーギーのマロンは見つけたとき、緑の葉っぱはすっかり食い散らかされ、「あれ、枝ごと丸坊主?」。食いしん坊の犯人は、枝1本の葉っぱをたいらげ、すでに隣りの枝に移っていました。「ははん。この音だ」。犯人は休むことなくムシャムシャと口を動かしています。「僕みたい」と、マロンがつぶやきました。
イモムシは足を取ったマロンのようにコロコロとしていました。わき目もふらずに、ムシャムシャムシャムシャ。じっと見つめてもムシャムシャ。「ウー」と唸ってみてもムシャムシャ。「ねえ。君はレモンの葉っぱしか食べないの?」と、マロンが虫の言葉で聞きました。
犯人のイモムシはチラッとマロンを見ましたが、すぐにまたムシャムシャ。「少しは、アジサイの葉っぱとかも食べたら?」と、マロンが言いましたが、聞こえない振りしてムシャムシャ。「好き嫌いはよくないな。僕は何でも食べるよ」と、マロンが言いましたが、おかまいなしにムシャッムシャムシャムシャ。「ねえ、聞こえてるの?」。
「聞こえてるよムシャムシャ」と、やっとのことで返事がありました。「僕らはムシャムシャ、食べるのが仕事だしムシャムシャ、レモンに生まれたらムシャムシャ、レモン以外はムシャムシャ、食べれないよ」。「そんなことしてたら、病気になっちゃうよ」と、マロンが言いました。「これ、食べてみる?」と、ドッグフードの残り物を1粒。「ええ?おいしくなさそうムシャムシャ」と、イモムシが言いました。「食べず嫌いはいけないよ」と、マロンがドッグフードを葉っぱの上に乗せました。
イモムシは頭とお腹とお尻がヒソヒソと話を始めました。「それ、食べてみてよ」と、イモムシのお尻がイモムシの頭に言いました。イモムシの頭は、初めての食べ物を食べてみました。「おいしい?」。「ゲッ!まずい」。「そんなことないはずだけどなあ?じゃあ、こっちの味は?」と、別のドッグフードを1粒。「今度は緑色だし、おいしそう」と、イモムシのお腹がイモムシの頭に言いました。「ギャア!犬って、こんなに不味いものを食べてるの?」と、イモムシの頭は一口食べて吐き出しました。「葉っぱの方が絶対においしい。食べてごらんよ」。
「ええ?葉っぱを食べるの?」。「食べてごらんよ」とイモムシのお腹が言いました。「食べてごらんよ」と、イモムシのお尻も言いました。マロンは勧められたレモンの葉っぱを口に入れてみました。「うーん。まずくはないけど」と、マロンが言いました。「マロンもイモムシになれるかもムシャムシャ」。「ぼ、僕、イモムシになりたくないもん」と、マロンが言いました。「でも、いつかはアゲハチョウになれるんだよ」と、イモムシのお尻が言いました。「そうそう、もうすぐアゲハチョウになれるんだよ」と、イモムシのお腹も言いました。「だから、それまでレモンの葉っぱをムシャムシャ、食べ続けるんだムシャムシャ」と、イモムシの頭が言いました。
「アゲハチョウになったら、また遊ぼうね」と、マロンが言いました。「でも、それが君だって分かるかなあ?」。「よし、じゃあ僕だって言う証拠にムシャムシャ、マロンのドッグフードのお皿にとまるよムシャムシャ。絶対に食べないけどねムシャムシャ」と、イモムシの頭が代表して言いました。「うん、楽しみに待っているね」。それから、しばらくした朝、寝ぼけまなこのマロンのお皿に、黄色くて美しいアゲハチョウが1羽、「マロン。おはよう」と、とまっていました。「おはようムシャムシャ」。
「誰が?何を?」。マロンが見つけたレモンの葉っぱが、誰かに食べられていました。コーギーのマロンは見つけたとき、緑の葉っぱはすっかり食い散らかされ、「あれ、枝ごと丸坊主?」。食いしん坊の犯人は、枝1本の葉っぱをたいらげ、すでに隣りの枝に移っていました。「ははん。この音だ」。犯人は休むことなくムシャムシャと口を動かしています。「僕みたい」と、マロンがつぶやきました。
イモムシは足を取ったマロンのようにコロコロとしていました。わき目もふらずに、ムシャムシャムシャムシャ。じっと見つめてもムシャムシャ。「ウー」と唸ってみてもムシャムシャ。「ねえ。君はレモンの葉っぱしか食べないの?」と、マロンが虫の言葉で聞きました。
犯人のイモムシはチラッとマロンを見ましたが、すぐにまたムシャムシャ。「少しは、アジサイの葉っぱとかも食べたら?」と、マロンが言いましたが、聞こえない振りしてムシャムシャ。「好き嫌いはよくないな。僕は何でも食べるよ」と、マロンが言いましたが、おかまいなしにムシャッムシャムシャムシャ。「ねえ、聞こえてるの?」。
「聞こえてるよムシャムシャ」と、やっとのことで返事がありました。「僕らはムシャムシャ、食べるのが仕事だしムシャムシャ、レモンに生まれたらムシャムシャ、レモン以外はムシャムシャ、食べれないよ」。「そんなことしてたら、病気になっちゃうよ」と、マロンが言いました。「これ、食べてみる?」と、ドッグフードの残り物を1粒。「ええ?おいしくなさそうムシャムシャ」と、イモムシが言いました。「食べず嫌いはいけないよ」と、マロンがドッグフードを葉っぱの上に乗せました。
イモムシは頭とお腹とお尻がヒソヒソと話を始めました。「それ、食べてみてよ」と、イモムシのお尻がイモムシの頭に言いました。イモムシの頭は、初めての食べ物を食べてみました。「おいしい?」。「ゲッ!まずい」。「そんなことないはずだけどなあ?じゃあ、こっちの味は?」と、別のドッグフードを1粒。「今度は緑色だし、おいしそう」と、イモムシのお腹がイモムシの頭に言いました。「ギャア!犬って、こんなに不味いものを食べてるの?」と、イモムシの頭は一口食べて吐き出しました。「葉っぱの方が絶対においしい。食べてごらんよ」。
「ええ?葉っぱを食べるの?」。「食べてごらんよ」とイモムシのお腹が言いました。「食べてごらんよ」と、イモムシのお尻も言いました。マロンは勧められたレモンの葉っぱを口に入れてみました。「うーん。まずくはないけど」と、マロンが言いました。「マロンもイモムシになれるかもムシャムシャ」。「ぼ、僕、イモムシになりたくないもん」と、マロンが言いました。「でも、いつかはアゲハチョウになれるんだよ」と、イモムシのお尻が言いました。「そうそう、もうすぐアゲハチョウになれるんだよ」と、イモムシのお腹も言いました。「だから、それまでレモンの葉っぱをムシャムシャ、食べ続けるんだムシャムシャ」と、イモムシの頭が言いました。
「アゲハチョウになったら、また遊ぼうね」と、マロンが言いました。「でも、それが君だって分かるかなあ?」。「よし、じゃあ僕だって言う証拠にムシャムシャ、マロンのドッグフードのお皿にとまるよムシャムシャ。絶対に食べないけどねムシャムシャ」と、イモムシの頭が代表して言いました。「うん、楽しみに待っているね」。それから、しばらくした朝、寝ぼけまなこのマロンのお皿に、黄色くて美しいアゲハチョウが1羽、「マロン。おはよう」と、とまっていました。「おはようムシャムシャ」。