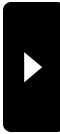2021年02月02日
街の洋食屋さん
街の洋食屋さんの名前は『サラダ』。もちろん、あのマルチーズのサラダが暮らす店です。「こんにちは」と、フラリと入ってきたのは、みんなが知っているこの街の北風市長でした。市長さんは、一番奥の席に座りました。サラダが、メニューをくわえて市長の席に来ました。「ああ、ありがとう」と、市長はメニューを受け取ると、サラダの頭をそっとなぜてくれました。「カレーライスをください」と、市長は言いました。サラダが奥に入って、ワンと鳴きました。厨房には、白い服の源助さんが座っていました。「あのう、カレーライスをお願いします」と、市長は、もう一度大きな声で言いました。「あいよ!」と、言ったような言わないような、源助さんは立ち上がり、大きな鍋の中を使い込んだレードルでゆっくりとかき回し始めました。
シャカシャカシャカシャカと、キャベツを切る気持ちのいい音がし始めました。市長が厨房の中をのぞくと、マルチーズのサラダが、巧みに包丁を使っていました。ザクザクザクザクと、黄緑色のキャベツを刻み、千切りキャベツが出来上がりました。「ほう」と、市長はその手際の良さに見とれていました。「見事だね」。サラダはお皿にご飯を盛り、そこに源助さんが大鍋のカレーをかけました。「はい。お待ち!」と、言ったような言わないような、市長の前に、千切りキャベツのついた大盛りカレーが現れました。
「あ、どうも」と、市長が顔を上げると、源助さんはもう、厨房の椅子に腰掛けていました。市長は、スプーンいっぱいのカレーライスを口に運びました。「美味しい!」と、思わず声に出してしまうほど、懐かしいカレーの味が口いっぱいに広がりました。サラダが刻んだ千切りキャベツを口に運びました。「なんて、美味しいんだ」と、市長は言いました。サラダは黙って、厨房の掃除をしていました。「腕のいい職人と働き者のマルチーズの店か」と、市長は感心したように言いました。
翌日、みんなが知っているあの北風市長がまたやってきました。マルチーズのサラダが、昨日と同じようにメニューをくわえて来ました。「ああ、ありがとう」と、市長は今日もサラダの頭をなぜてくれました。「カツライスをお願いします!」。厨房の中では源助さんが立ち上がりました。サラダがシャカシャカザクザクとキャベツを切り始めた音がしました。源助さんは、トンカツの油を切りました。サラダがお皿にご飯を盛りました。別のお皿にトンカツが乗せられ、千切りキャベツがたっぷりと添えられました。「うん。美味しい」と、市長は言いました源助さんは椅子に腰掛け、サラダは黙って厨房の掃除をしていました。
次の日も、次の日も、市長がやって来ました。サラダが刻んだ千切りキャベツの添えられたハヤシライスも食べました。オムライスも食べました。どれもこれも、なぜか忘れられない懐かしい味でした。でも、どうしたことか、その洋食屋さんでは、他の客の姿を見ることがありませんでした。「どうしたんだろう?こんなに美味しいこの店が、このままでは潰れてしまう」と、市長は心配しました。「そうだ。この美味しい洋食屋さんを、みんなにも教えてやろう」と、市長は目を輝かせて言いました。源助さんは椅子に腰掛け、サラダは掃除をしていて、市長の顔は見ませんでした。
市長室に戻った市長が、職員に言いました。「洋食屋のカレーは最高の味だね。千切りキャベツも美味しいし」。職員は誰も何も答えませんでした。「洋食屋のカツライスはこの街一番だね。千切りキャベツもシャキシャキだし」。でも、職員は誰も何も言いませんでした。「どうしたんだい?なんで、誰も何も言わないのかな?」と、市長が聞きました。長い時間の沈黙のあと、明日定年を迎える職員がようやく口を開きました。「あの洋食屋さんは、もうありませんよ。一週間前に店を閉じました」と、首を振りました。「そんなことはない。私がはじめて行ったのが一週間前。それから毎日行っているけど、店は開いているよ」と、市長は言いました。明後日定年を迎える職員が、市長の前に地図を広げました。街の地図のスミの方に、赤い鉛筆でくっきりと引かれた線がありました。「これは、何のしるしだったかな?」と、市長が聞きました。「その線は、新しく道路ができるしるしです」。「じゃあ、あの店は、道路にかかるのか」と、市長が聞きました。「市長が引いた線です。私たちはみんな反対したのですが…」と、4日後に定年を迎える職員が言いました。
市長は庁舎の一番高い部屋に、一人で登りました。そこから、あの洋食屋さん『サラダ』が見えました。「ああ、大変だ!」と、市長は言いました。洋食屋さんの近くに、黄色のブルドーザーが近づいていました。洋食屋の厨房には、椅子に腰掛ける源助さんと、真っ白なマルチーズのサラダの姿が見えたような気がしました。「誰か来てくれ!」と、市長は職員を呼びました。「道路の工事は中止にする。すぐにブルドーザーを止めてくれ!」と、市長が言いました。「私の最後の仕事でよければ」と、今日定年を迎えた職員が言いました。「何とかしてください。お願いします」と、みんなが知っているこの街の北風市長が、気をつけの姿勢で深々と頭を下げました。
シャカシャカシャカシャカと、キャベツを切る気持ちのいい音がし始めました。市長が厨房の中をのぞくと、マルチーズのサラダが、巧みに包丁を使っていました。ザクザクザクザクと、黄緑色のキャベツを刻み、千切りキャベツが出来上がりました。「ほう」と、市長はその手際の良さに見とれていました。「見事だね」。サラダはお皿にご飯を盛り、そこに源助さんが大鍋のカレーをかけました。「はい。お待ち!」と、言ったような言わないような、市長の前に、千切りキャベツのついた大盛りカレーが現れました。
「あ、どうも」と、市長が顔を上げると、源助さんはもう、厨房の椅子に腰掛けていました。市長は、スプーンいっぱいのカレーライスを口に運びました。「美味しい!」と、思わず声に出してしまうほど、懐かしいカレーの味が口いっぱいに広がりました。サラダが刻んだ千切りキャベツを口に運びました。「なんて、美味しいんだ」と、市長は言いました。サラダは黙って、厨房の掃除をしていました。「腕のいい職人と働き者のマルチーズの店か」と、市長は感心したように言いました。
翌日、みんなが知っているあの北風市長がまたやってきました。マルチーズのサラダが、昨日と同じようにメニューをくわえて来ました。「ああ、ありがとう」と、市長は今日もサラダの頭をなぜてくれました。「カツライスをお願いします!」。厨房の中では源助さんが立ち上がりました。サラダがシャカシャカザクザクとキャベツを切り始めた音がしました。源助さんは、トンカツの油を切りました。サラダがお皿にご飯を盛りました。別のお皿にトンカツが乗せられ、千切りキャベツがたっぷりと添えられました。「うん。美味しい」と、市長は言いました源助さんは椅子に腰掛け、サラダは黙って厨房の掃除をしていました。
次の日も、次の日も、市長がやって来ました。サラダが刻んだ千切りキャベツの添えられたハヤシライスも食べました。オムライスも食べました。どれもこれも、なぜか忘れられない懐かしい味でした。でも、どうしたことか、その洋食屋さんでは、他の客の姿を見ることがありませんでした。「どうしたんだろう?こんなに美味しいこの店が、このままでは潰れてしまう」と、市長は心配しました。「そうだ。この美味しい洋食屋さんを、みんなにも教えてやろう」と、市長は目を輝かせて言いました。源助さんは椅子に腰掛け、サラダは掃除をしていて、市長の顔は見ませんでした。
市長室に戻った市長が、職員に言いました。「洋食屋のカレーは最高の味だね。千切りキャベツも美味しいし」。職員は誰も何も答えませんでした。「洋食屋のカツライスはこの街一番だね。千切りキャベツもシャキシャキだし」。でも、職員は誰も何も言いませんでした。「どうしたんだい?なんで、誰も何も言わないのかな?」と、市長が聞きました。長い時間の沈黙のあと、明日定年を迎える職員がようやく口を開きました。「あの洋食屋さんは、もうありませんよ。一週間前に店を閉じました」と、首を振りました。「そんなことはない。私がはじめて行ったのが一週間前。それから毎日行っているけど、店は開いているよ」と、市長は言いました。明後日定年を迎える職員が、市長の前に地図を広げました。街の地図のスミの方に、赤い鉛筆でくっきりと引かれた線がありました。「これは、何のしるしだったかな?」と、市長が聞きました。「その線は、新しく道路ができるしるしです」。「じゃあ、あの店は、道路にかかるのか」と、市長が聞きました。「市長が引いた線です。私たちはみんな反対したのですが…」と、4日後に定年を迎える職員が言いました。
市長は庁舎の一番高い部屋に、一人で登りました。そこから、あの洋食屋さん『サラダ』が見えました。「ああ、大変だ!」と、市長は言いました。洋食屋さんの近くに、黄色のブルドーザーが近づいていました。洋食屋の厨房には、椅子に腰掛ける源助さんと、真っ白なマルチーズのサラダの姿が見えたような気がしました。「誰か来てくれ!」と、市長は職員を呼びました。「道路の工事は中止にする。すぐにブルドーザーを止めてくれ!」と、市長が言いました。「私の最後の仕事でよければ」と、今日定年を迎えた職員が言いました。「何とかしてください。お願いします」と、みんなが知っているこの街の北風市長が、気をつけの姿勢で深々と頭を下げました。